 ござる
ござるこんにちは、ござるです。



地方上級は難しすぎると言われているけど、自分は合格できるかな…?
こんな不安を抱えていませんか?
実は僕も、受験生のときに同じ気持ちでした。
ネットで調べると「難しすぎる」という声ばかりだったので、正直ビビってました。
でも、結論から言うと、地方上級は難しすぎるわけではありません。努力次第で十分に合格できます。
この記事では、
- なぜ「地方上級=難しすぎる」と言われるのか
- 実際に合格した僕の体験談
- そして、合格するための具体的な対策
をまとめました。



リアルな体験や本音で解説していくので、ぜひ参考にしてください。
【結論】地方上級は難しすぎ?→努力次第で合格できる!


「地方上級は難しすぎる」と言われますが、結論から言えば、努力すれば十分に合格可能です。
僕も受験生のときに受けましたが、「そこまで恐れないでOK」というのが正直な感想です。
もちろん、難しいと言われる要素はいくつかあって
- 試験範囲が広い
- 過去問が公開されていない
- 倍率が高い
- 学歴が必要そうに見える
なんかですが、これらはあなたが諦める理由にはなりません。



自分はそんなに勉強できるほうじゃないよ
と思うかもしれませんが



大丈夫!いけます!
この後、それぞれの「難しいと言われる理由」を詳しく見ながら、「合格するためにどう対策したらいいか」を解説していきますね。
地方上級が「難しすぎる」と言われる4つの理由
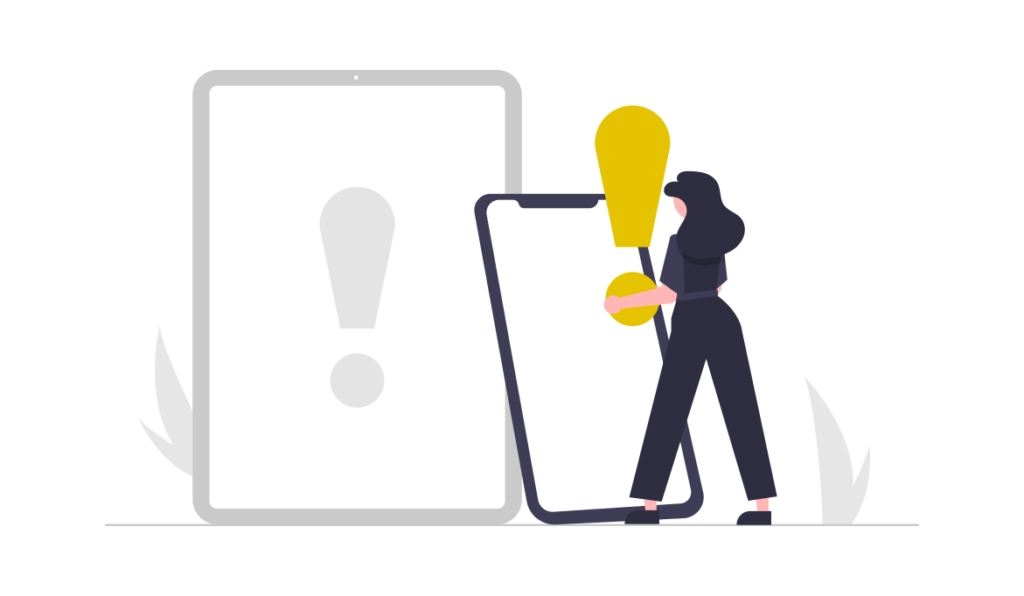
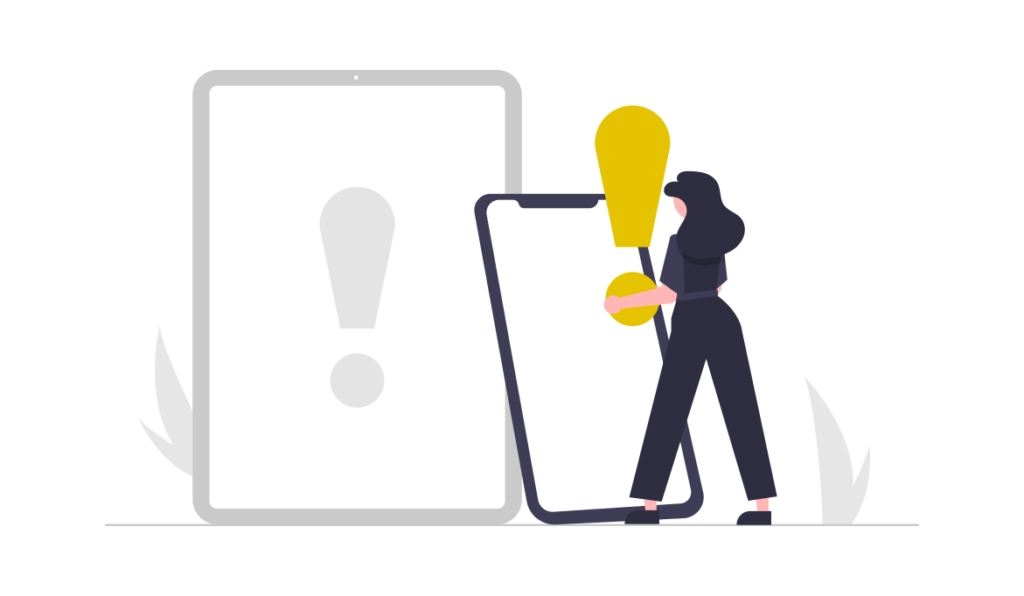
理由1 試験範囲が膨大で科目数が多い
地方上級の勉強でまずしんどいのは、試験範囲が広すぎることです。
教養と専門を合わせると、科目はざっと30科目。
教養科目
専門科目
- 英文
- 現代文
- 数的推理
- 判断推理
- 資料解釈
- 数学
- 物理
- 化学
- 生物
- 地学
- 日本史
- 世界史
- 地理
- 政治
- 法律
- 経済
- 社会
- 憲法
- 行政法
- 民法
- 刑法
- 労働法
- 経済原論
- 財政学
- 政治学
- 行政学
- 社会政策
- 国際関係
- 経営学



大学受験でも、5教科7科目だったのに、範囲広すぎない…?
と思いますよね。
正直、僕も最初にこれを見たときは「無理ゲーじゃん」と思いました。



ただ、実際に勉強してみると「全科目をガチで仕上げる必要はない」ことがわかりました。
科目ごとの範囲の広さは大学受験では全然ないし、勉強しない「捨て科目」を作ってもOK。
あと、才能が必要な科目もないので、やればやれだけ伸びます。(これ重要)
地方上級の合格に必要な勉強時間は、約1000時間と言われていて、これは1日3時間の勉強を1年間、1日6時間の勉強を6ヶ月できれば達成できます。



それって普通に大変じゃない…?
実際に勉強をした感想を言うと
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
確かに大変です。



ただ、勉強を習慣化して、コツコツ積み重ねていけば達成できる勉強量だと思います。
なので、無理ゲーというよりは「自分が勉強を継続できるか」の戦いになってきますね。
理由2 過去問が非公開で勉強しにくい
地方上級の厄介ポイントは、過去問が公開されていないことです。
持ち帰りが禁止なので、ネットを探しても載っていないんですね。



じゃあどうしたら良いんだ!
っていう話ですが、一応再現問題が出版されているので、それを使用して勉強するのが一般的です。
受験生が記憶を頼りにまとめた問題だから完璧じゃないけど、傾向をつかむには十分。
僕も最初は「こんなんで大丈夫か?」と思ったけど、何周かやっているうちに出題パターンが読めるようになりました。
地方上級の問題は少しクセがあって、王道だけじゃなくマイナーな知識も出たりします。
だからこそ、再現問題に早めに触れて「こういう感じか」と慣れておくのが大事かなと。



ただ、基本的には国家一般職などの試験勉強と変わらないので、そこまで気にしなくても大丈夫です!
理由3 試験の倍率が高く見える
地方上級は、未だに人気が高く、試験の倍率が高めです。
令和4年のデータですが、地方公務員全体の倍率は5.2倍。
受ける職種や自治体によって変わってきますが、大体の平均はこのぐらいですね。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
5人に1人しか受からないなら無理じゃん…
と僕も最初は思いました。
でも、大丈夫。実際はそこまで心配しなくてOKです。
なぜなら、受験者全員が本気で合格を目指しているわけではないからなんですね。



民間企業に就職する予定だけど一応受験しに来た人



受かる気はないけど記念受験した人
こうした人も含まれるので、実質的な倍率はもっと低いです。
最初の倍率は高くても、筆記試験が終わると、2倍程度に落ち着きます。
ちょっといけそうな気がしてきましたよね。
↘️さらに近年、地方上級の倍率は減少傾向にある(2025年現在)
もっと朗報を言うと、近年、試験の倍率は下がってきています。
これは、地方上級に限った話ではないのですが、就活生が公務員離れしつつあります。
理由としてはこんな感じ。
- 民間の・初任給アップ・柔軟な働き方(リモート等)が進み、就活生が民間に流れやすい
- 公務員試験は準備負担が重く、民間就活とのスケジュール両立が難しいと感じる学生が多い
- 民間は内定が早いため、公務員試験の途中に辞退が発生しやすい
つまり、公務員試験=狭き門というのは昔のイメージです。
これは受験生にとって大きなチャンス。
倍率が下がっている=しっかり勉強した人が報われやすい環境になっているから、挑むだけの価値はあると思いますね。
理由4 合格者は高学歴ばかりというイメージ



地方上級は高学歴の人しか合格できないのでは?
こんな不安を持つ人、多いと思います。
僕も受験生のとき、正直そう思ってました。
旧帝大とか早慶MARCHみたいな高学歴ばっかり受かってるんだろうなって。
でも、実際に入庁してみたら全然そんなことなかったです。
僕は地方の政令指定都市に入庁しましたが、一番多かったのは、地元や周辺の国公立大学出身。
次いで、地元私立とかでしたね。
つまり、公務員試験に学歴フィルターは存在しなくて、筆記で点を取って、面接でアピールできれば誰でも合格できます。
地方上級の問題の難易度は、繰り返し勉強すれば理解できるレベルで、才能は必要ありません。
やればやるだけ成績が伸びるので、努力でカバーすることが可能。



なので、学歴は気にしなくてOKです!
ここまで、「地方上級が難しすぎると言われる理由」について解説しました。
でも実際には、工夫すればどれも乗り越えられるものばかりです。
じゃあどうやって合格するか?



ここからは、僕自身が地方上級試験で実際にやった「3つの対策」を紹介します。
合格者の僕が実際にやった3つの対策
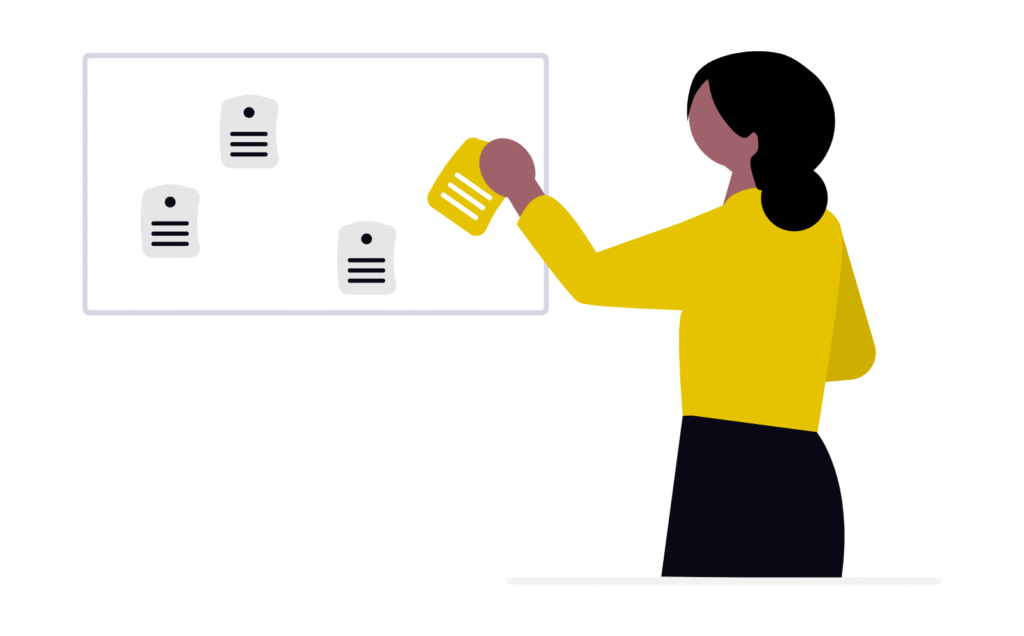
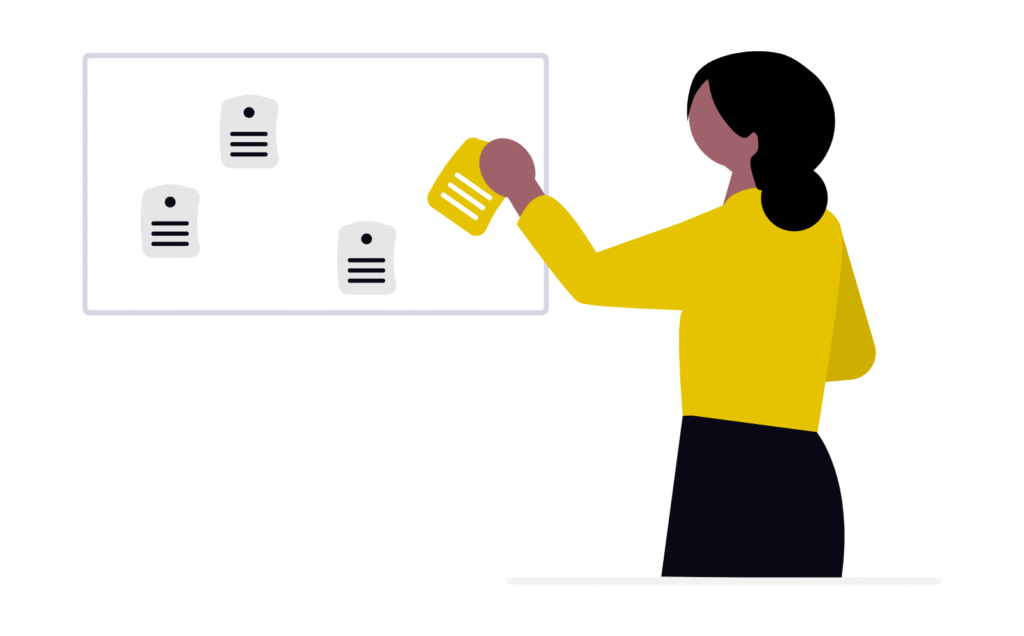
対策1 面接重視の傾向に備える
地方上級は、近年、面接重視の傾向にあります。
いくら筆記試験で点数が良かったとしても、面接での印象が良くないとフツーに落とされてしまいます。
なので、面接対策はガッツリやってください。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
僕も正直、最初は面接がすごく苦手でした…
でも、模擬面接を受けて、フィードバックをもらって、修正して…これを繰り返すうちにだんだん慣れてきました。
🗣️面接が上達する方法
- 面接対策のノウハウをブログやYouTube、書籍で学ぶ
- 模擬面接に挑戦する
- 面接官からフィードバックをもらって修正する
これのひたすら繰り返しで、やり方はシンプルです。



面接もやった分だけ伸びるので、怖がらずに場数を踏むことが大切です。
対策2 勉強時間1000時間+筆記6割を目標にする
勉強するうえで、目標みたいなのがあるとわかりやすいですよね。
地方上級に合格するための目安は、勉強時間1000時間/筆記6割突破です。
まず、勉強時間1000時間は、1日3時間の勉強を1年、6時間の勉強を半年続けれたらクリアできます。



僕もトータルの勉強時間は、1000時間ぐらいでした。
次に筆記試験のボーダー。6割と書きましたが、実際はもう少し低くても突破できると思います。
ただ、余裕を持って6割目標で良いと思いますね。
自治体によって異なるので一概には言えませんが、大体こんな感じです。
対策3 国家一般職対策で兼用する
地方上級は過去問が非公開と言いましたが、実際には、国家一般職対策をしていれば十分対応できます。
国家一般職は、地方上級と同じような試験形式や日程で構成されています。
つまり、国家一般職の対策をしていれば、ほとんど地方上級の対策もできるので、一石二鳥なんですね。
多分、地方上級の受験生の多くが、国家一般職を併願すると思うので、この兼用スタイルで勉強するのが一番良いと思いますね。
【体験談】僕が「難しすぎ」と思った瞬間と乗り越えた方法
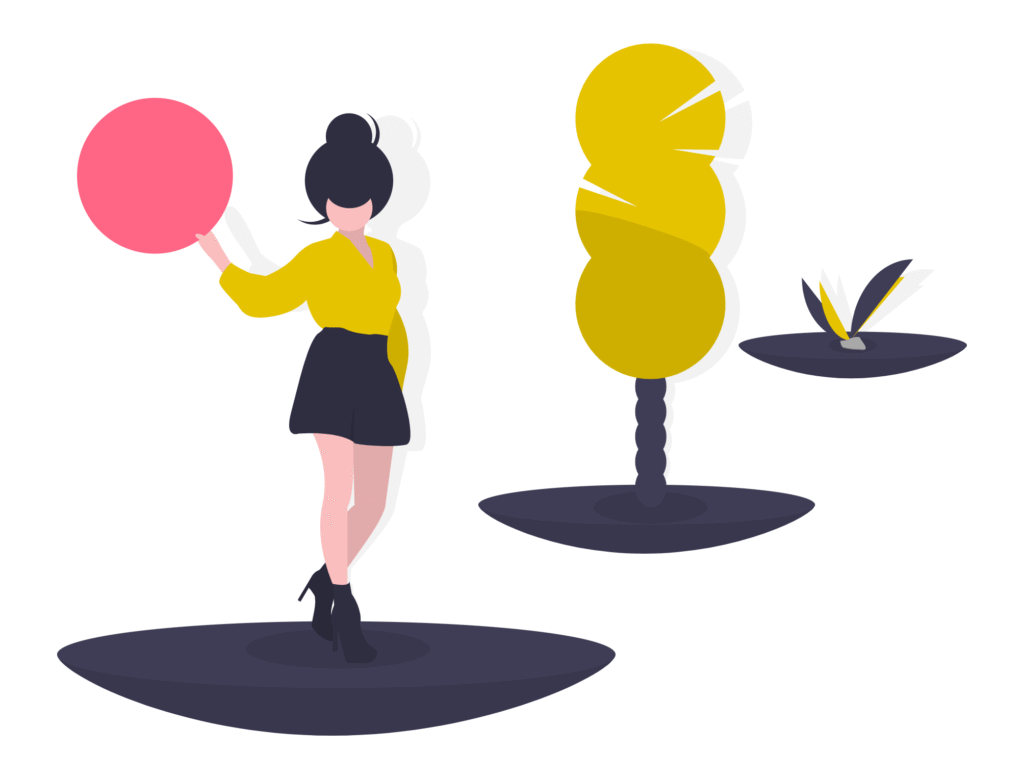
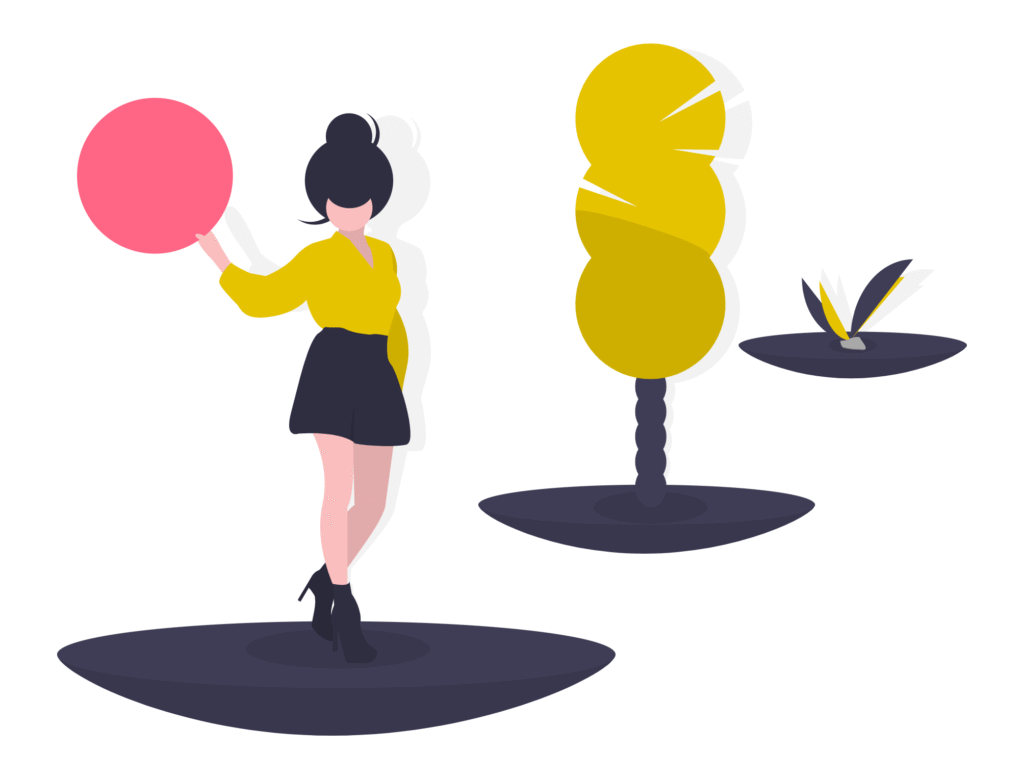
僕が「難しすぎ」と本気で思った瞬間は、勉強を始めたばかりの頃です。
30科目もあると知ったときは「これは無理だ」と感じましたし、最初は机に向かうモチベすら湧きませんでした。
なので、「とりあえず30分だけ」と小さな目標を立てました。
でも正直、最初の頃は30分やっても全然頭に入らなくて、「やっぱり向いてないかも」と落ち込むこともありました。
それでも毎日30分を積み重ねていくうちに、気づけば「勉強するのが当たり前」に。



振り返ると、これはめちゃくちゃ大きかったですね。次第に何時間も勉強できるようになりました。
地方上級は「問題がめちゃくちゃ難しい」というよりは、「勉強のモチベを維持するのが難しい」試験なんですよね。
だからこそ、いかに継続できるかが合否のカギだと思います。



僕は独学で勉強していましたが、予備校や大学講座に通っている人は、仲間と切磋琢磨できたらやり切れると思うよ!
【まとめ】地方上級は難しすぎない!挑戦する価値あり!
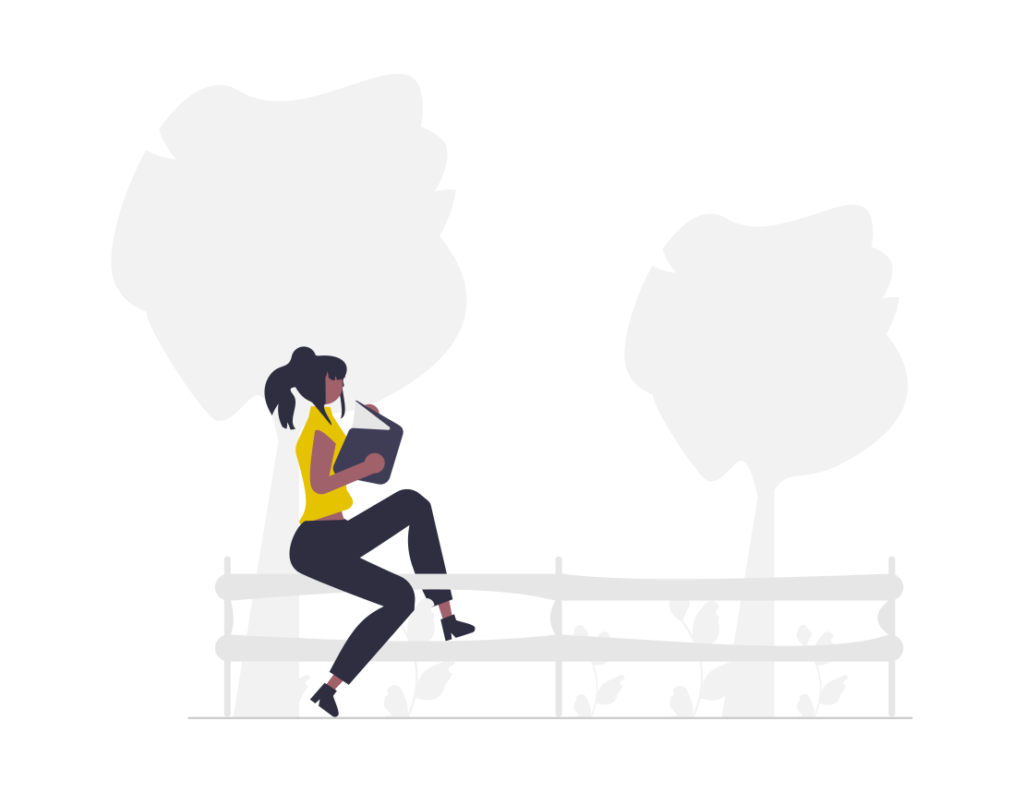
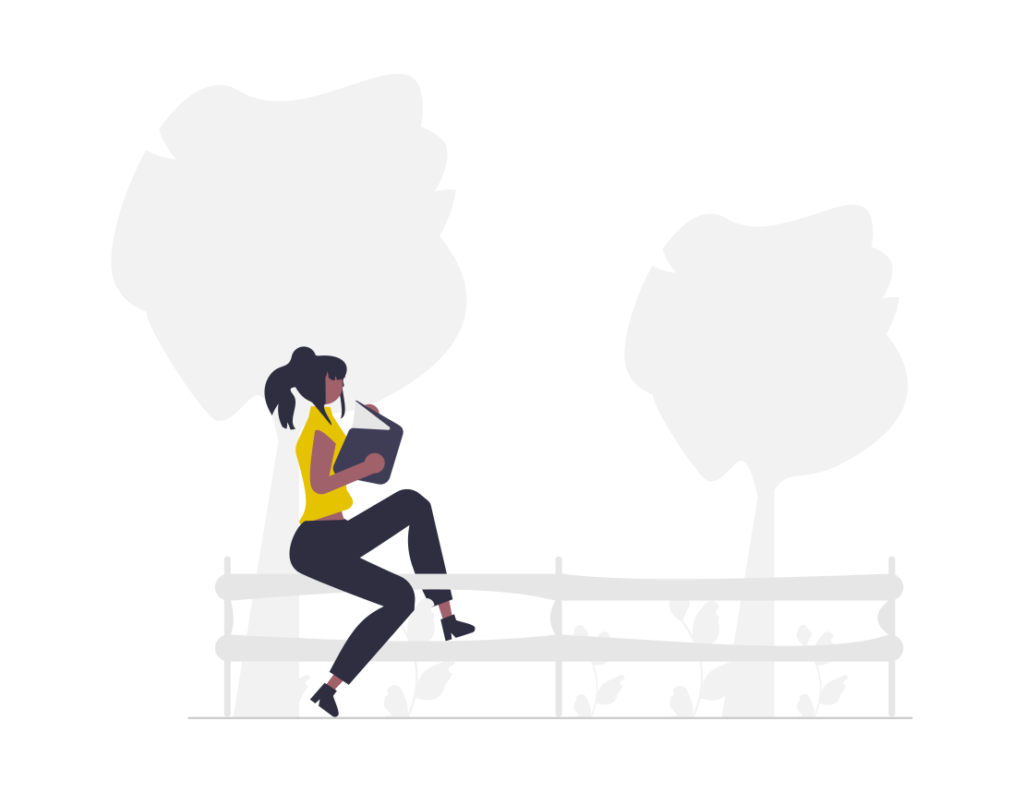
ここまで「地方上級は難しすぎる」と言われる理由と、その対策について解説してきました。
結論はシンプルで、地方上級は難しすぎる試験ではありません。
範囲が広いとか、過去問が非公開とか、不安になる要素はありますが、ひとつずつ工夫して取り組めば十分に合格を狙えます。
なので、挑戦する価値は十分ありますよ。
一歩ずつでいいので、合格に向けて歩みを進めていきましょう!
このブログでは、他にも地方上級に関する記事を書いていますので、良かったら見てください。
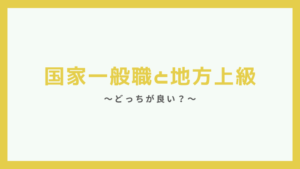
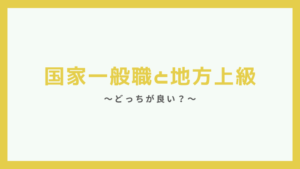
地方上級に関するよくある質問(FAQ)
- そもそも地方上級って何?
-
地方上級は「大卒程度」の地方公務員採用試験のこと。
県庁とか政令指定都市の職員を採るときに使われる区分です。
実は正式な試験名じゃなくて、受験業界での通称なんですよね。
- 地方上級は国家一般職より難しい?
-
正直、レベル感はほぼ同じです。
試験範囲や出題傾向も近いので、国家一般職の勉強をしていれば地方上級もカバーできます。
地方上級はクセのある問題が多いので、そういう意味では少しだけ難しいかもしれません。
- 地方上級は独学でも合格できる?
-
できます。僕も独学でした。
ただ、独学だとモチベ維持が一番大変。
その分「勉強仲間を作る」「SNSで記録する」とか、自分なりの工夫はあった方がいいです。
不安なら予備校や通信講座を活用してもいいけど、独学でも十分戦えますよ。
- 地方上級は低学歴(Fラン)でも合格できる?
-
できます。
公務員試験において、学歴は採点基準には含まれません。
合格に必要なのは学歴じゃなくて、筆記で点を取る力+面接での印象です。
僕の周りでも正直言えば低学歴(Fラン)の人も全然合格してました。
なので、学歴を理由に諦める必要は全くないですね。
以上になります。



最後まで読んでくれてありがとうございました!
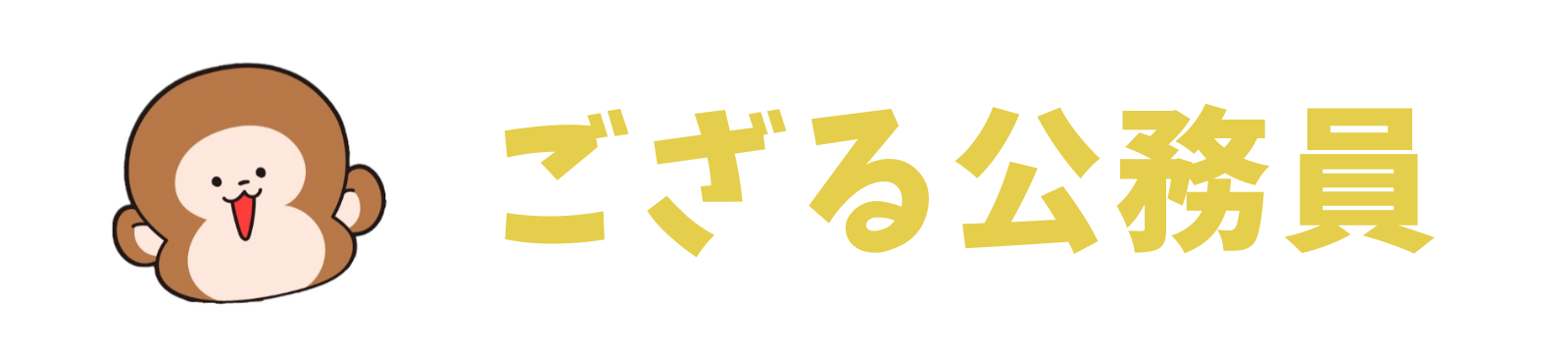






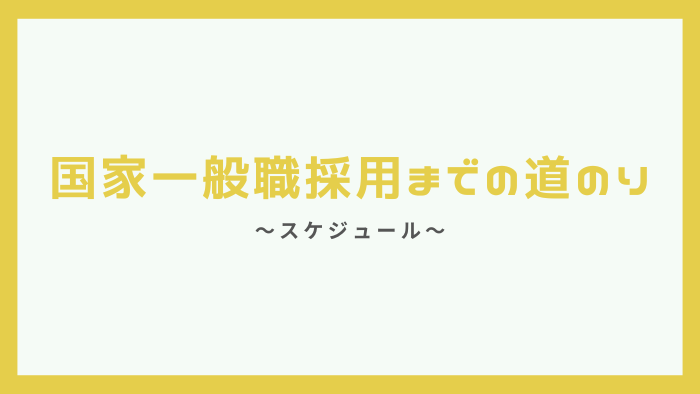
コメント