 ござる
ござるこんにちは。ござるです。
今回は、専門科目「民法」について解説していきます。
受験生の中には



民法を捨てようかな…
と思っている人もいるのではないでしょうか。



ちょっと手をつけてみたけれど、範囲は膨大で内容もよくわからない…
確かに捨てたくなる気持ちもわかります。



ですが、ちょっと待ってください!
僕が皆さんに真剣にアドバイスするなら
民法を捨てるのはもったいないです!(一部を除いて)
公務員試験に合格するためにも、勉強したほうが良いです。



なぜなの!?



その理由を解説していくね!
民法を捨てるのがもったいない理由


理由1 問題数が多く重要科目だから
「民法」は問題数が多いので、公務員試験の重要科目です。
試験別の問題数
- 国家総合職 12問
- 国家一般職 10問(選択)
- 裁判所事務官 13問
- 特別区Ⅰ類 10問(選択)
見てわかるように、10問以上出題されている試験が多いですよね。基本的にこれらの試験を受ける受験生は、「民法」を勉強したほうが良いです。(併願だったとしても)
問題数が多い科目を捨てるのはリスキーですからね。
ただし、上に挙げていない試験では、問題数が少なかったりします。
- 地方上級全国型 4問
- 地方上級関東型 6問
- 地方上級中部・北陸型 7問
- 国税専門官 6問
- 市役所A日程 5問
上に挙げた試験しか受けない受験生は、最悪「民法」を捨てるという選択肢もあります。



個人的には勉強したほうが良いと思っていますが、どうしても「難しい」と感じた場合は、他の科目に全力を注ぐのはアリです。
理由2 覚えてしまえば安定した得点源になるから
民法は難しい。
ですが、覚えてしまえば安定した得点源になり、強い味方になるんです。
例えば、国家一般職では16科目のうち8科目(全40問)を選択しますが、民法はⅠとⅡ合わせて10問あります。
例年の難易度がそれほど変わらないことから安定した科目なので、できれば選択したいですね。
民法は範囲が膨大なため、問題で聞かれる知識自体はそれほど細かいものではありません。
憲法なんかは難しくないので、細かい知識が問われたりするんですけどね。



学習難易度は高めですが、覚えてしまえばその分見返りのある科目なので、頑張って取り組んでほしいです。
民法の勉強法


では、ここからは民法の勉強法について解説していきます。
民法も結局のところ暗記科目なので



気合で覚えろ!
と言いたいところなんですが、間違った勉強をしてしまうと、民法は全然覚えられないです。
やってはいけないのは、民法を「暗記」と思って何も考えずにただ頭に知識を入れていく勉強です。
憲法や行政法はそれでもなんとかなりますが、民法は覚える内容自体が複雑なので、全く頭に残りません。
ではどうしたら良いかというと、民法は「暗記」ではなくまず「理解」から入らなければいけません。
民法では、判例や通説が出てきますが、様々な利害関係のケースを覚える必要があります。
複雑ですが、利害関係などを図でイメージしながら「理解」ができれば、問題に対応できるようになります。



暗記科目というイメージを忘れて、体系的に学習するようにしてください!
そして、勉強の流れとしては、理解用参考書でインプットをしてから、過去問などでアウトプットをひたすら繰り返していきます。
他の科目の場合は、アウトプットをしながらインプットするような同時並行の学習が可能だったりしますが、民法の場合は、きっちりインプットの過程を経てアウトプットをしないと、挫折してしまいます。
先ほど述べたように「暗記」よりも「理解」することを意識して、理解用参考書を最低3周してみてください。
民法の参考書


次に参考書について解説していきます。
使う参考書
- 理解用参考書(インプット用)
- 過去問(アウトプット用)
まず、インプットするための理解用参考書についてですが、
僕のオススメは、「寺本康之の民法ザ・ベスト ハイパーシリーズ」です。
僕も実際に使いましたが
- 「理解」しながら勉強できる
- 図解でわかりやすく学ぶことができる
- 途中に確認問題があり、知識の定着が図ることができる
などから、民法のインプットにぴったりな一冊だと思います。
民法は、近年改正が続いていますが、参考書を選ぶときは最新の情報が載っているものを購入してください。



上で挙げたシリーズも改訂版の方を購入してね。
そして、アウトプットするための過去問は
「スーパー過去問ゼミシリーズ」がオススメです。
公務員試験の参考書の王道で、良問が多く収録されているので、これを使っておけば間違いないです。
民法の勉強を始める時期


民法の勉強については、憲法や行政法を学習したら取り組むべきかなと思います。
勉強の難易度
民法>行政法>憲法
ぐらいのイメージでして、最初に勉強すると、つまづいてしまう可能性があるからです。
ただ、重要科目には変わりないので、早めに手をつけられたら良いですね。
受ける試験にもよりますが、夏頃から勉強を始められたらベストなのではないでしょうか。
まとめ:民法を捨てるのはもったいない!根気強く勉強しよう


今回は、「民法を捨てるべきか」について解説しました。
受験生に嫌われがちな科目ですが、知識が身につけば、強い味方になるので、是非諦めずに勉強してみてください。
民法だけでなく、他の専門科目についても、こちらの記事で解説していますので、良かったらみてください。


以上になります。



最後まで読んでくれてありがとうございました!
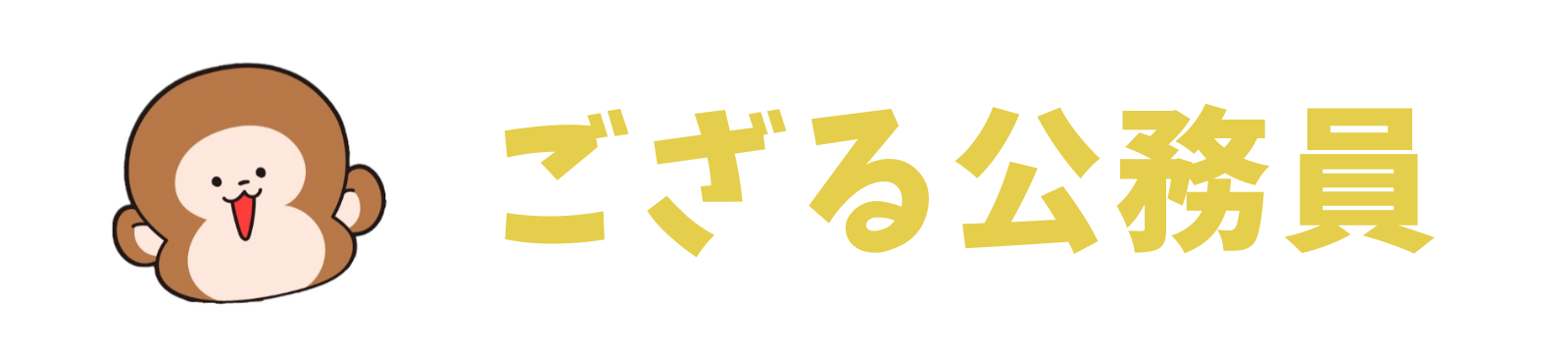






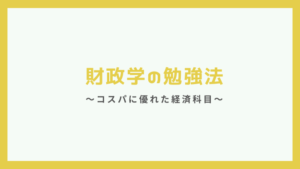
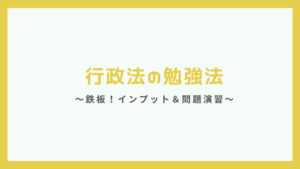




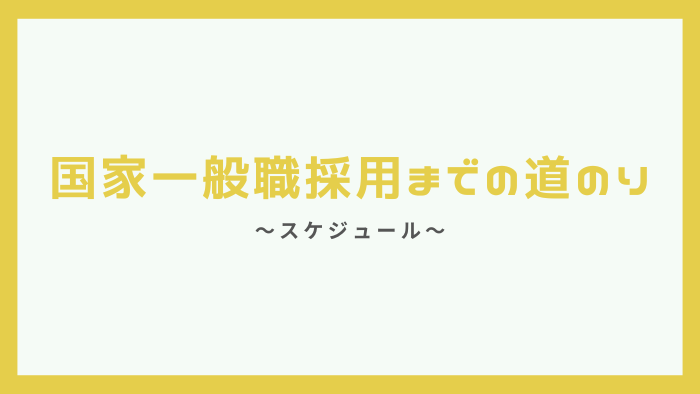
コメント