 ござる
ござるこんにちは。ござるです。
今回は、公務員試験の専門科目「財政学」の勉強法について解説します。



財政学は勉強するべき?



財政学って難しいの?



どうやって勉強すればいいの?
こういった疑問にお答えします。
財政学をこれから勉強する人の参考になれば幸いです。
財政学の出題状況


| 試験 | 出題数 |
|---|---|
| 地方上級 | 3問 |
| 国家一般職・国家総合職 | 5問(選択形式) |
| 特別区 | 5問(選択形式) |
あまり聞いたことのないマイナー科目かもしれませんが、公務員試験では結構出題されてますね。
地方上級なら3問、国家一般職・総合職・特別区なら選択科目ですが5問出題されます。
国家一般職・総合職・特別区で「財政学」を選択する人は、当然勉強しなければいけませんし、地方上級の受験生であっても、3問出題されるので、勉強したい科目ですね。
財政学の勉強難易度


財政学の内容自体はそれほど難しくありません。易しめだと思います。
イメージといったら「経済系暗記科目」みたいな感じですね。
ミクロマクロでつまづいた人も、財政学は、基本的に用語と数値を覚えていくだけなので、なんとかなります。
さらに、ミクロマクロで覚えた内容が結構出てくるので、ミクロマクロ→財政学の順番で勉強すれば、スムーズに学習できますよ。



財政学はかなりコスパの良い科目!
財政学の出題内容


財政学の出題は主に制度系、事情系、理論系に分けることが出来ます。
まず、制度系というのは、財政のルールに関する知識についてで、例えば、国の財政制度や地方財政、税制など、幅広く日本の財政のしくみが出されます。
次に、事情系というのは、日本や各国の財政事情についてで、例えば、当初予算や財政収支などのデータが問われたりします。
最後に、理論系は、政府の経済活動が経済に与える影響など、理論的考察に対する知識を扱います。例えば、乗数効果や公共財などですね。
ただ、この理論系で学習する範囲は、実はミクロ経済学・マクロ経済学の内容と重なっている場合が多いんです。
つまり、ミクロマクロを勉強している人にとっては制度・事情系の知識を覚えるだけで良いというわけです。
さらに、事情系でも、最新のデータを扱うので、既に「速攻の時事」などで時事の勉強をしている人は知っている知識が多いため、あまり時間をかけずに仕上げることができます。



思ったより覚えることが多くないんだ!
財政学の参考書
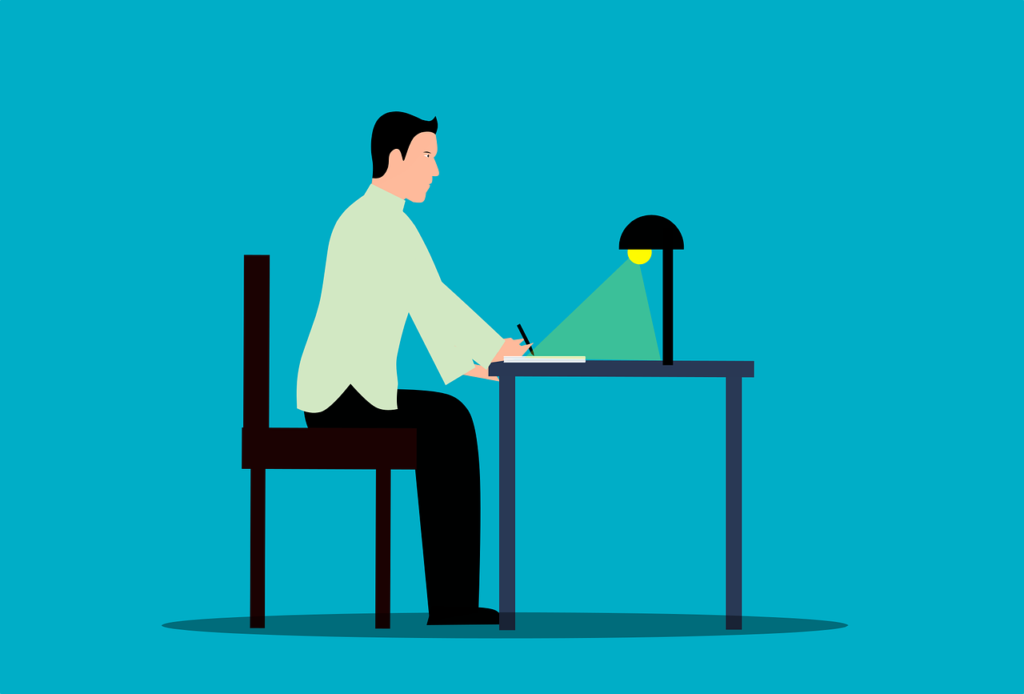
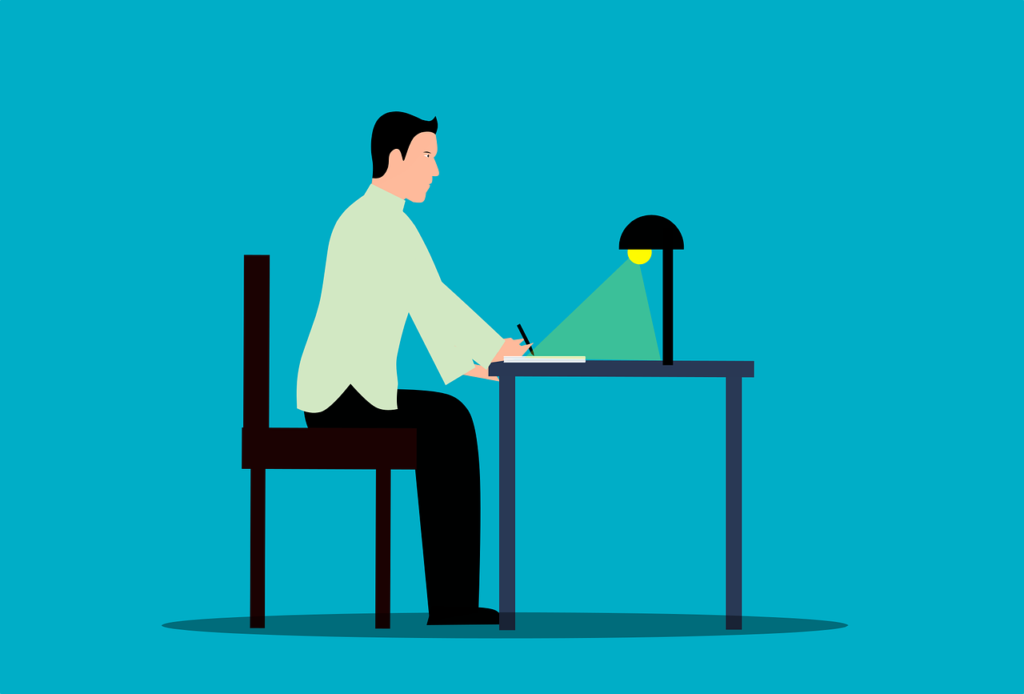
財政学の勉強は「スーパー過去問ゼミ財政学」を使って行います。
基本的に財政学の勉強にインプット用の参考書は必要ありません。
スーパー過去問ゼミは問題集ですが、テーマごとに重要ポイントがまとめられているため、インプットも問題なくできます。
ただ、ひとつ注意しなければいけないのが、最新版の「スーパー過去問ゼミ財政学」を使用するということです。
財政データは毎年更新されるため、古いもので勉強してしまうと、試験で出題される前年度までのデータが載っておらず、「せっかく覚えたのに点が取れない」なんてことになります。



そうならないためにも、毎年1~2月頃に発売される最新のスーパー過去問ゼミを買うようにしてね!
財政学の勉強を始める時期
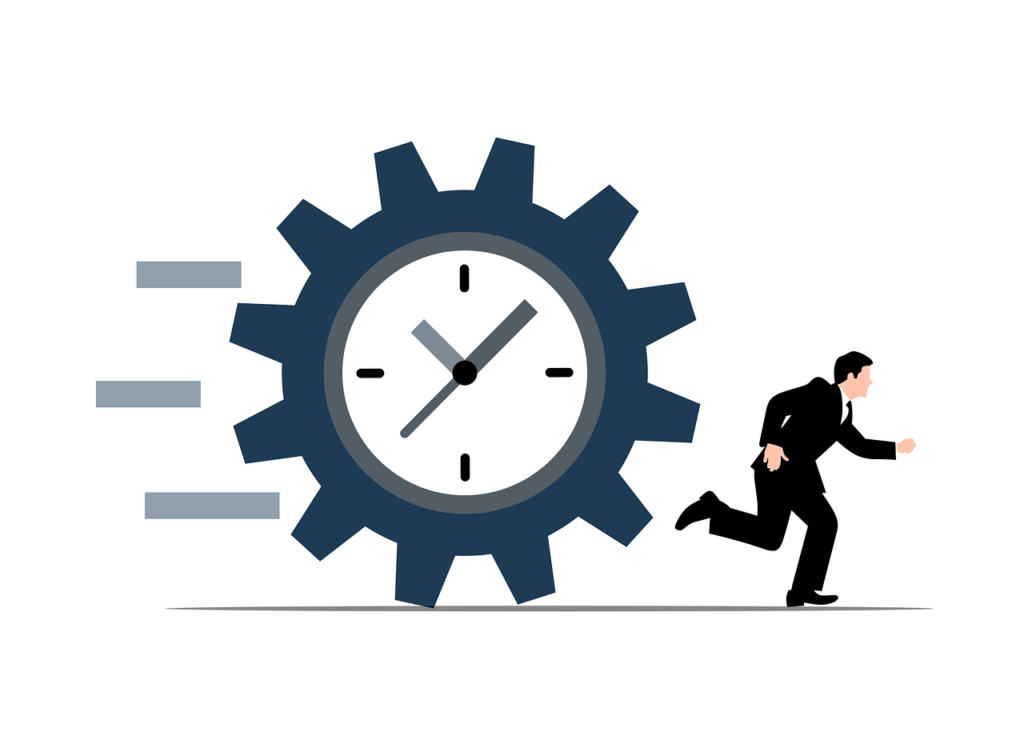
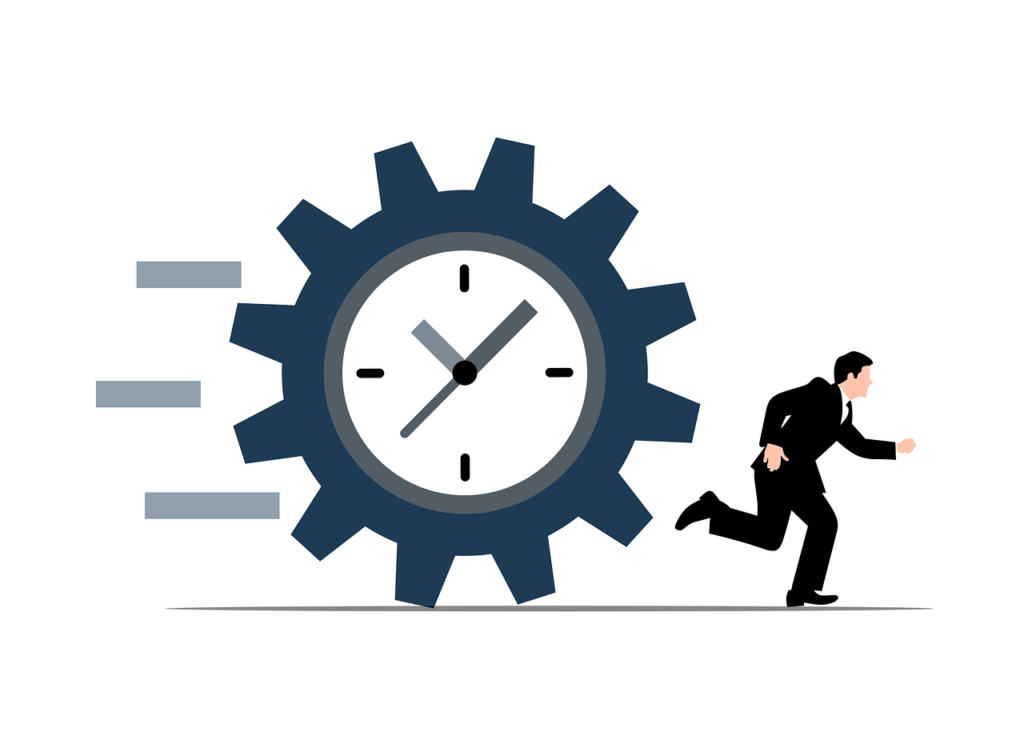
財政学の勉強は基本的に1~2月以降で大丈夫です。
先ほど言ったスーパー過去問ゼミの最新版が発売されてからで問題ありません。
ミクロやマクロを勉強している人、時事の勉強をしている人は、試験2か月前からでも問題ないと思います。



捨てようか迷ってる人も、コスパの良い科目なので、直前期でも時間があれば勉強するのをオススメします。
以上が財政学の勉強法になります。



最後まで読んでくれてありがとうございました!
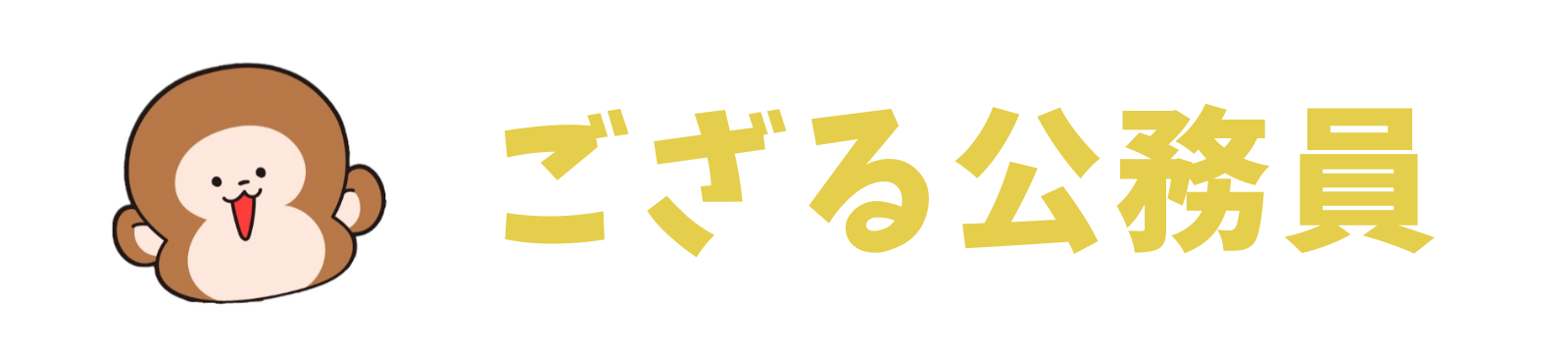
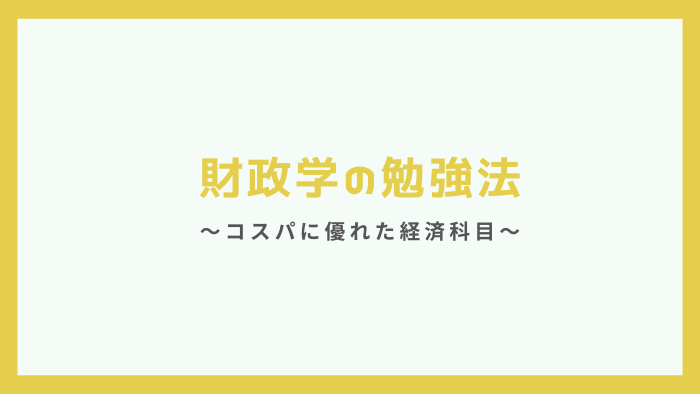




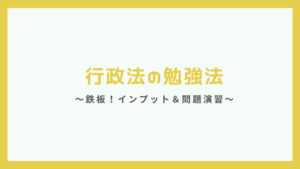




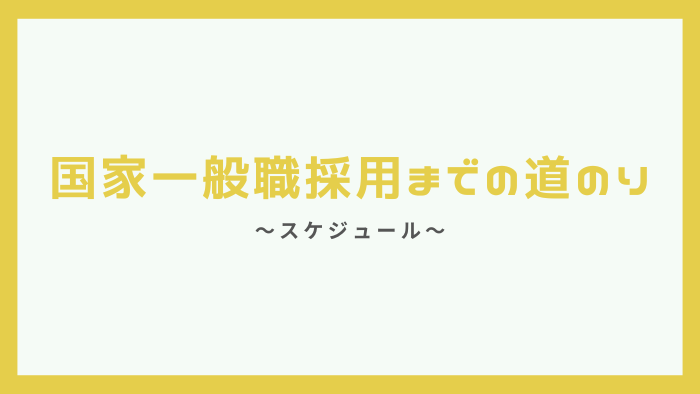
コメント