国家一般職の専門科目って、16科目もあるから

どれを選べばいいか分からない…
と悩みますよね。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
僕も受験生のとき、「これで合ってるのか?」「本番で全然解けなかったらどうしよう」と不安でいっぱいでした。
そこでこの記事では、選ぶべき国家一般職の専門科目を、ランキング形式で紹介します。
「得点源になる科目」「地雷科目」「併願で使いやすい科目」まで、すべて解説していきます。
💡 この記事でわかること
- 国家一般職の専門科目16科目を「おすすめ順」で整理したランキング
- 得点源になる科目・避けたほうがいい地雷科目の見分け方
- 併願を見据えたコスパの良い科目選択
- 試験本番で「どの科目を選ぶか」迷わない判断基準



ではさっそく、おすすめ科目ランキングTOP3から見ていきましょう!
国家一般職の専門科目おすすめランキング
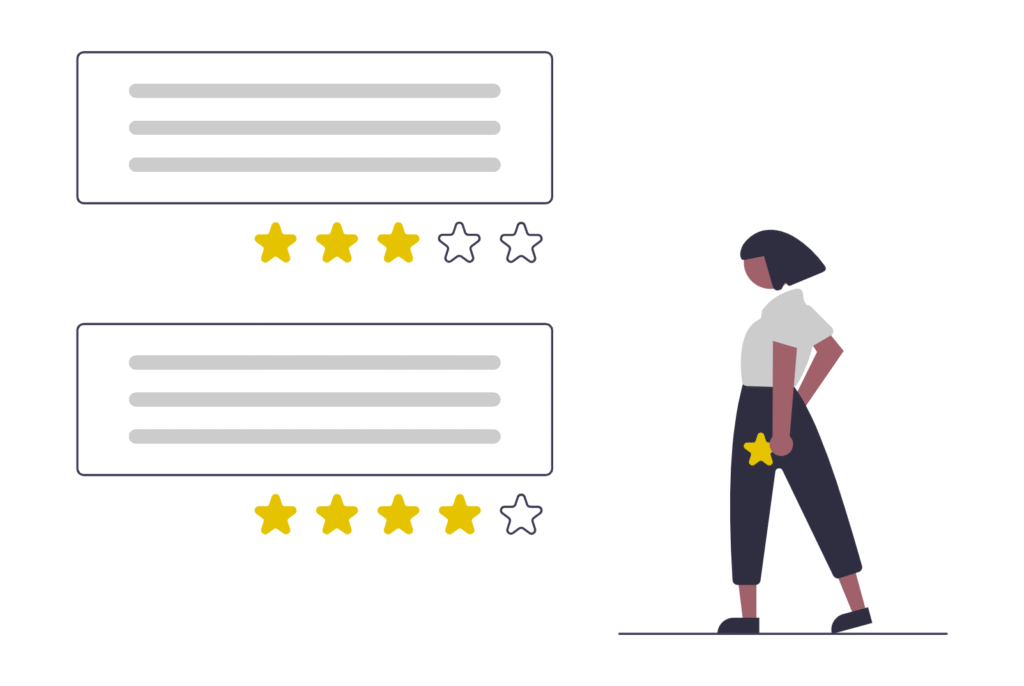
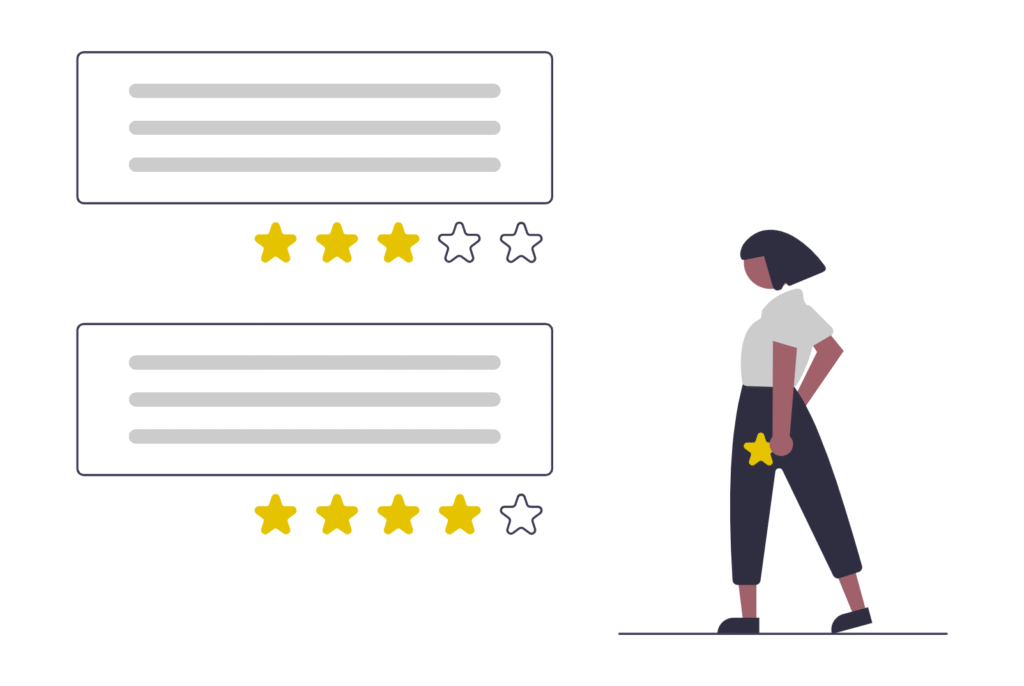
まず結論。
国家一般職の専門科目の中で、得点源になりやすく・コスパが良く・併願にも使える科目TOP3はこちらです👇
| 順位 | 科目 | 特徴 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 🥇1位 | 憲法 | 安定して得点でき、ほぼ全員が選択。併願にも必須。 | ★★★★★ |
| 🥈2位 | 行政法 | 他試験でも使える鉄板科目。覚えにくいが努力が結果に直結。 | ★★★★☆ |
| 🥉3位 | ミクロ経済学 | 苦手でも理解しやすく、問題難易度が安定している。 | ★★★★☆ |
憲法・行政法・ミクロ経済学は、どの年度でも安定して得点源になる科目。



実際に僕もこの3科目を軸に合格点を取ることができました。
ではここから、各科目を定番・準主力・中堅・地雷の4カテゴリに分けて、一つずつ解説していきます。
💎 まず選ぶべき定番科目
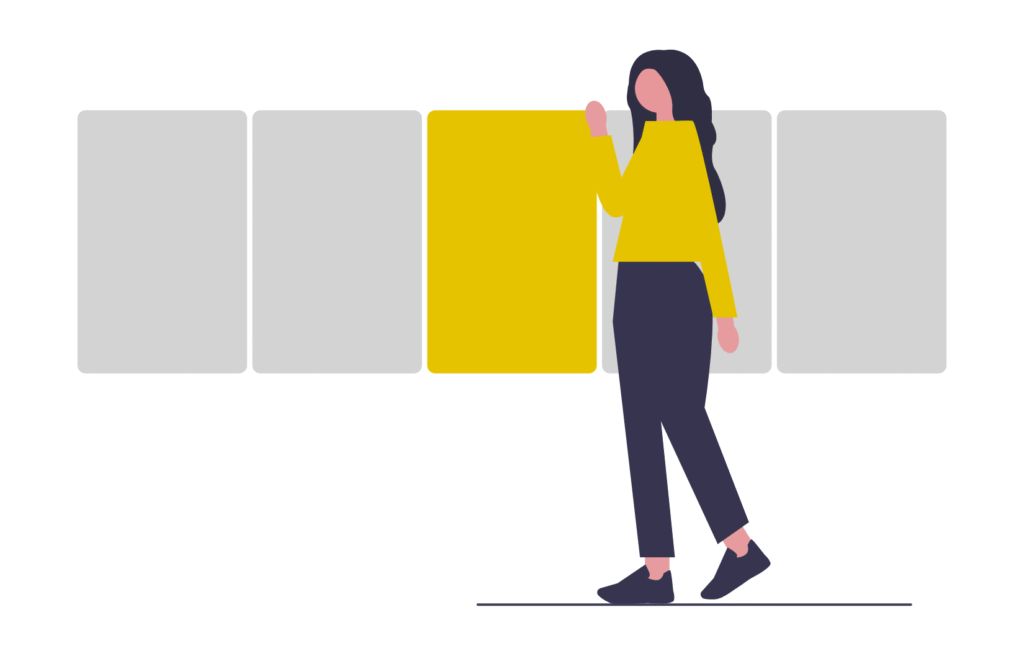
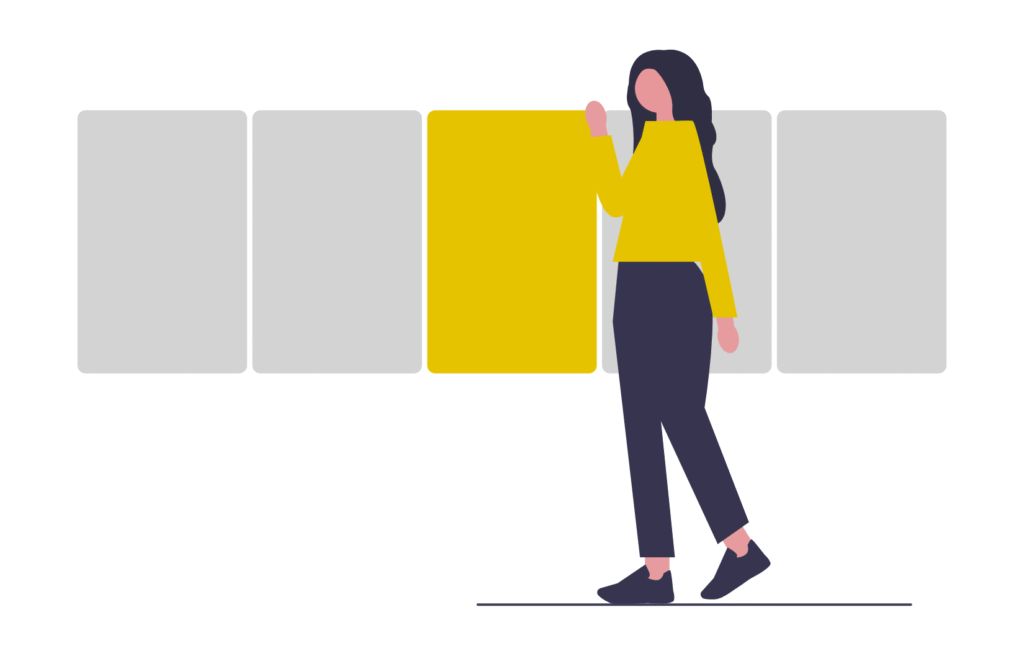
憲法|安定して得点できる必須科目
- 難易度 ★★★★★
- コスパ ★★★★★
- 汎用性 ★★★★★
憲法は、内容が分かりやすく、暗記が中心。
初学者でも得点しやすく、他試験との併用率も非常に高い科目です。
出題傾向も安定しており、地方上級や市役所でも頻出。
法律系科目の中でも「最初に仕上げるべき1科目」です。



みんな大好き憲法!
💡ポイント解説
科目自体が易しいため、若干、細かい知識の出題があるのは注意が必要です。
行政法|他試験でも使える鉄板科目
- 難易度 ★★★★☆
- コスパ ★★★★☆
- 汎用性 ★★★★★
ほぼすべての試験で出題される「必修級の定番科目」。
「憲法+行政法」は合格者の定番セットです。
用語がやや難しく感じるかもしれませんが、暗記量はまずまず、慣れれば安定して得点できます。



味のないガムを噛み続けるような科目!
💡ポイント解説
難易度としては「憲法<行政法<<民法」で、憲法よりも少し難しく、民法よりは易しいぐらいです。
ミクロ経済学|経済が苦手でも狙いやすい得点源
- 難易度 ★★★★☆
- コスパ ★★★★☆
- 汎用性 ★★★★☆
ミクロ経済学は理論が複雑ではなく、苦手な人でも点数が伸びやすいです。
国家一般職では、それほどクセのある問題は出題されないので、過去問で十分対策できます。
僕も数学はかなり苦手なタイプですが、ミクロ経済学はほとんどいけました。



経済系が苦手でもミクロは大丈夫なはず!
💡ポイント解説
数学の知識はそこまで必要なく、「連立方程式」「微分」「指数の計算」ぐらいです。
⚙️得点源にできる準主力科目


マクロ経済学|理解は難しいが、割り切れば得点可能
- 難易度 ★★★☆☆
- コスパ ★★★★☆
- 汎用性 ★★★★☆
マクロは理論理解に時間がかかる科目。
ミクロと比較すると難しいと感じる人が多いです。
僕も一から理論を理解しようとしましたが、結局よくわからないままだった部分もありました。
ただし、出題パターンがほぼ固定されているため、過去問を繰り返せば得点を安定させやすいです。



なんかよくわからないけど、問題は解けるなって状態を目指すのがマクロ経済学です。
💡ポイント解説
「理論を全部理解しよう」とせず、過去問の「問題タイプ」を覚えるのがコツ。暗記感覚でOK!


民法Ⅰ・Ⅱ|範囲が広い難関科目だが、安定して得点できる
- 難易度 ★★☆☆☆
- コスパ ★★★☆☆
- 汎用性 ★★★★☆
民法は公務員試験屈指のボリューム科目。
内容は複雑ですが、Ⅰ・Ⅱで10問出題されるため、得意にすれば得点源として安定感を発揮します。
なので、「捨て科目」にせず、頑張って選ぶほうが絶対良いです。
難易度が例年安定していることもグッド。



嫌われがちな科目だけど、覚えてしまえば強い味方!
💡ポイント解説
最初から全範囲を追うより、「頻出分野から潰す」が鉄則。
財政学・経済事情|範囲が狭くコスパ良い
- 難易度 ★★★★☆
- コスパ ★★★★★
- 汎用性 ★★★☆☆
「財政学・経済事情」は、勉強する範囲が狭くコスパに優れた科目です。
ミクロ・マクロの知識と重なる部分が多く、短期間でも仕上げやすい。
出題範囲が狭い分、しっかり覚えれば安定して点が取れる「穴場科目」。



経済系のおいしいとこ取り科目!
💡ポイント解説
最新データ(税制・財政赤字・物価動向)もしっかり把握しておこう。
時事対策も合わせてやっておくと、さらに点が取りやすくなるよ。
📚 中堅どころの選択可能科目
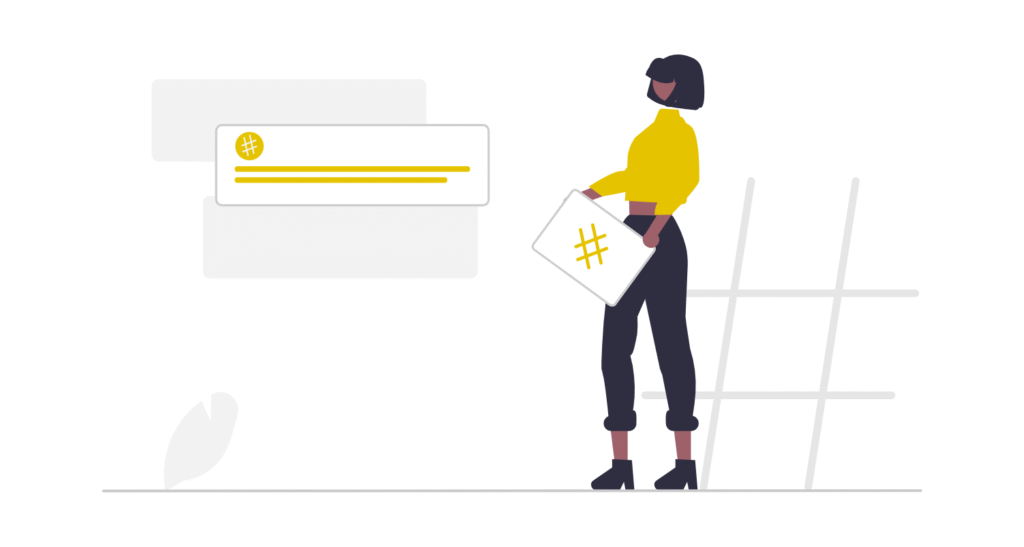
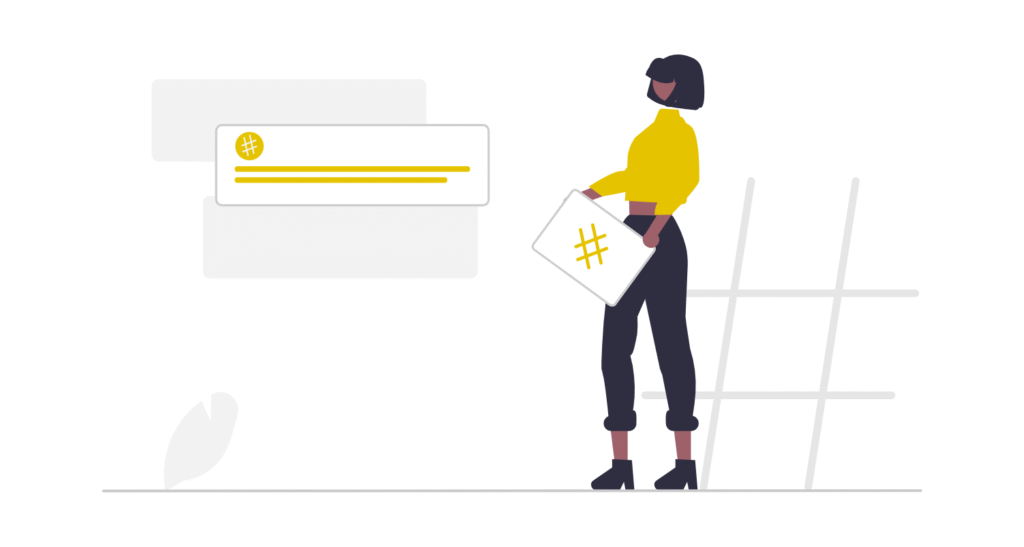
行政学・社会学|暗記中心なマイナー科目、併願先次第
- 難易度 ★★★☆☆
- コスパ ★★☆☆☆
- 汎用性 ★★☆☆☆
行政学と社会学は、暗記中心のマイナー科目ですが、出題傾向が安定しており、努力がそのまま得点につながりやすい科目です。
一方で、範囲が広かったり、他試験で使う機会が少なかったりするため、併願先次第で優先度を判断するのがポイントです。



地雷科目というほどじゃないけど、コスパはそこまで良くないって感じですね。
💡ポイント解説
出題範囲が広いので、完璧を目指さないことが大事だったりする。
英語(基礎)|得意なら高得点を狙える
- 難易度 ★★★☆☆
- コスパ ★★★☆☆
- 汎用性 ★★☆☆☆
難易度は共通テストより少し難しいレベル。
苦手な人は避けたほうが無難だけど、得意な人なら挑戦するのはアリ。
過去問を一度見て、解けそうか判断してみてください。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
「久しぶりに英語触る人」には地獄…
💡ポイント解説
TOEIC650点以上の実力があれば戦えます。
教育学・心理学|専願向けのサブ科目
- 難易度 ★★★☆☆
- コスパ ★★★☆☆
- 汎用性 ★☆☆☆☆
内容自体はそこまで難しくないが、他試験では出番がほぼない。
国家一般職専願の人や、大学で専攻している人なら◎。



専願じゃないなら基本選択しなくて良いかな!
💡ポイント解説
勉強するなら「スーパー過去問ゼミ」を何周かしよう。
⚠️ 年度によって難易度が高くなる地雷科目
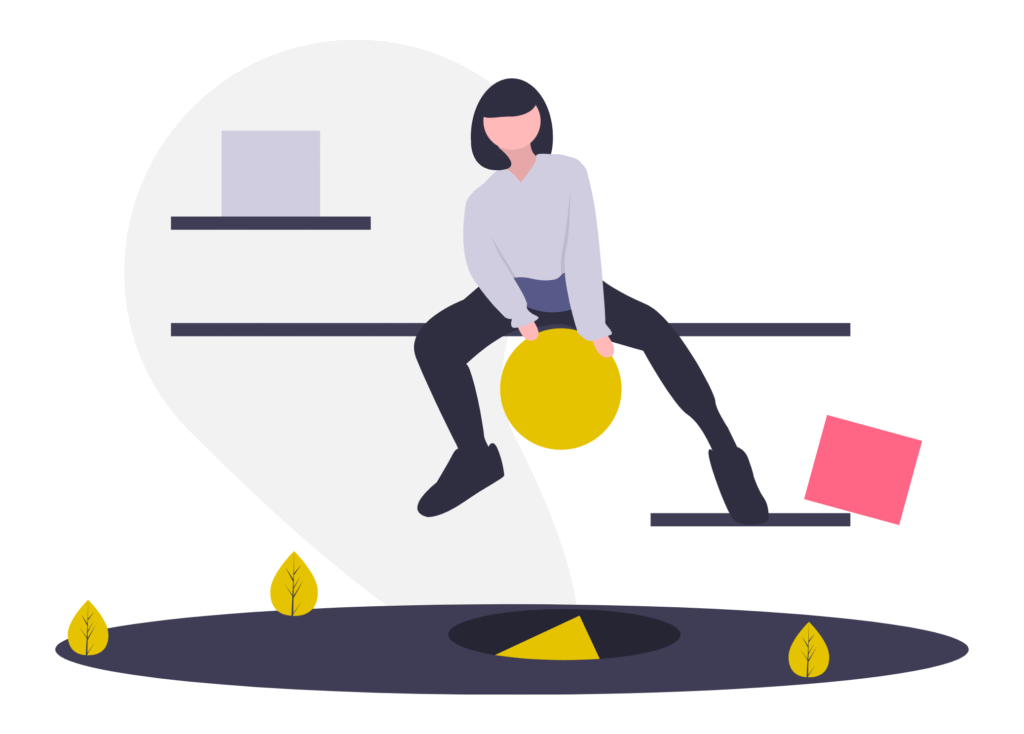
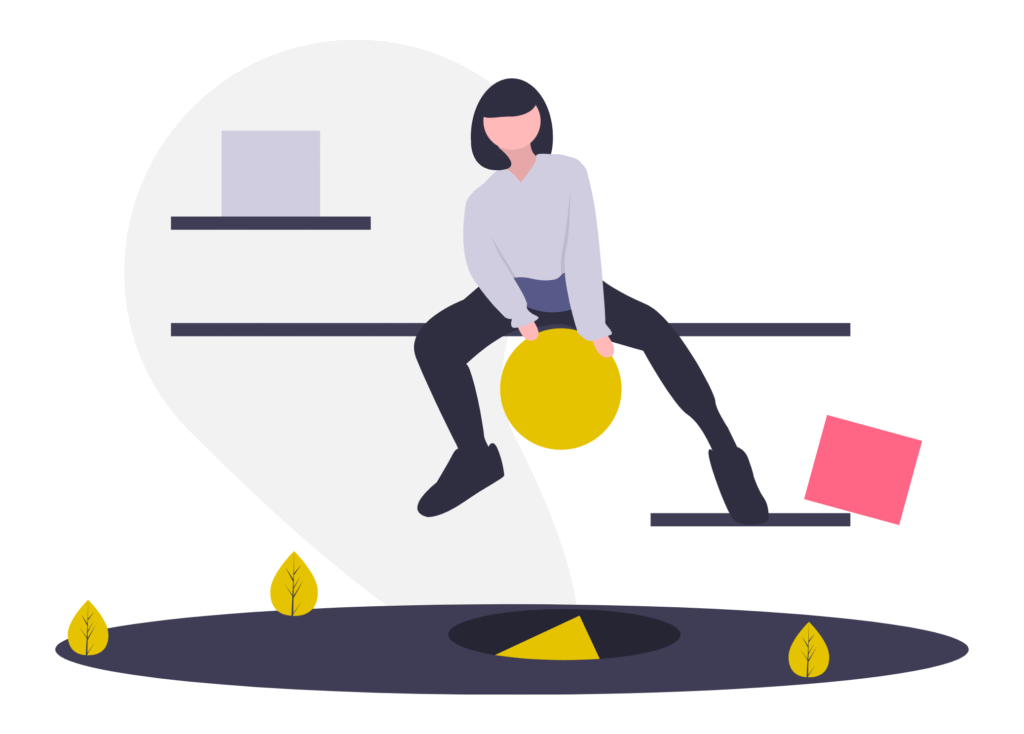
政治学|出題範囲が広すぎて安定しない
- 難易度 ★★☆☆☆
- コスパ ★★☆☆☆
- 汎用性 ★★☆☆☆
政治学は「理論・思想・制度・時事」など範囲がとにかく広く、年度によって出題傾向がガラッと変わるのが最大のネック。
基礎固めをしても「当たる年・外れる年」の差が激しく、安定して得点を取りづらい科目です。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
受験生のときは何も知らずに政治学を解いたよ…
💡ポイント解説
範囲が膨大で的が絞りにくいため、気合の暗記が必要。
国際関係|年度ごとのテーマ差が激しい
- 難易度 ★★☆☆☆
- コスパ ★★☆☆☆
- 汎用性 ★★☆☆☆
国際関係は、出題分野が「外交史・国際政治・条約・現代情勢」とバラバラで、年によって「当たり外れ」が極端です。
範囲が広いので、対策するのがかなり難しいです。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
去年出たテーマが翌年ゼロとか普通にあるんだよね
💡ポイント解説
時事問題が強い人以外は避けるのが無難。「勉強量に対して成果が読めない」です。
経営学|問題がマニアックで難易度が高め
- 難易度 ★★☆☆☆
- コスパ ★★☆☆☆
- 汎用性 ★★☆☆☆
経営学は、経営理論やマーケティングの知識が問われます。
文系科目の中でも専門性が高く、経営系の学部出身者以外にはハードルが高いです。
暗記科目なら、他にもっと汎用性のある科目があるので、優先順位は低めですね。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
経営学部じゃないとキツいってことか…
💡ポイント解説
他試験でもあまり出題されないため、汎用性が低い。同じ時間を「財政学」や「行政学」に回した方が効率的。
英語(一般)|英語上級者向けのハイリスク科目
- 難易度 ★☆☆☆☆
- コスパ ★★☆☆☆
- 汎用性 ★☆☆☆☆
名前こそ「一般」ですが、TOEIC800点〜帰国子女レベルでないと太刀打ちできません。
文章量も多く、語彙レベルも高いので、普通の受験生が選ぶ科目ではありません。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
「一般」に騙されて解いたら撃沈するよ…
💡ポイント解説
長文のスピード・語彙力・読解慣れが全て求められる。英語が得意でも「安全ではない科目」として認識しておこう。
試験本番での選び方・判断基準
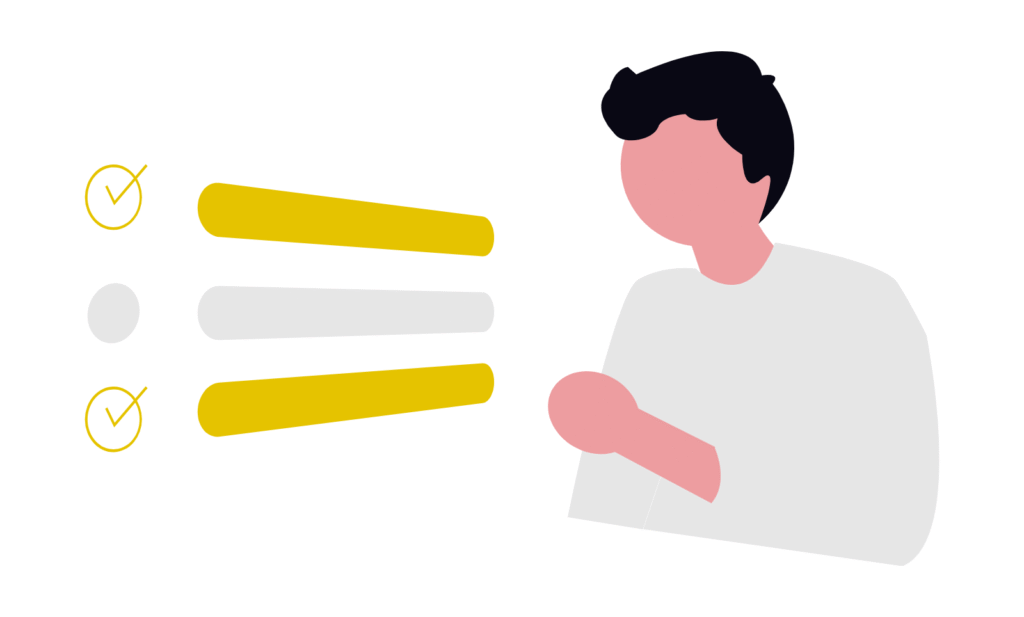
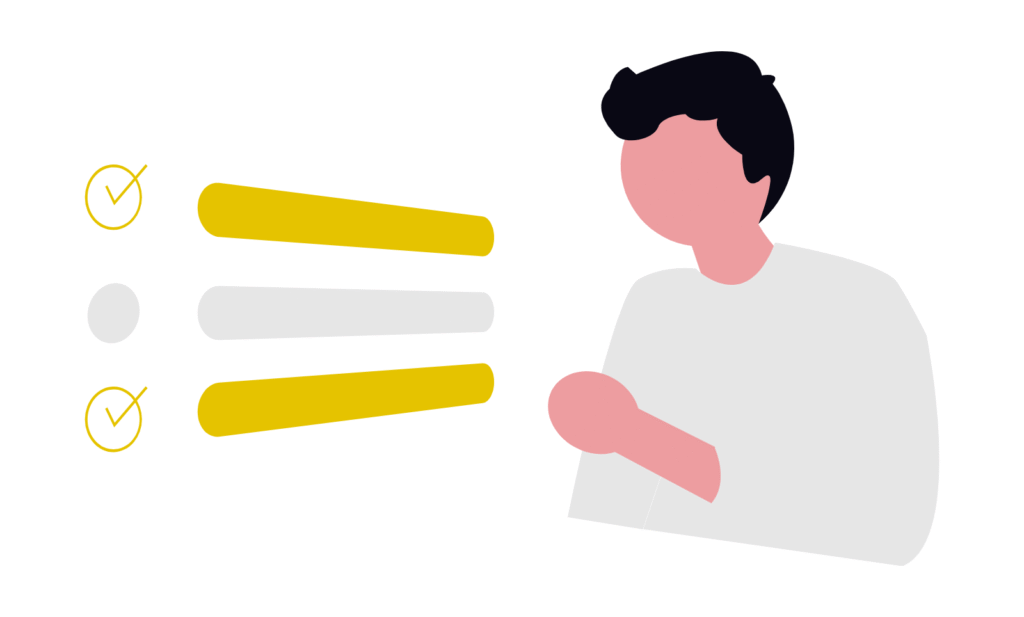
試験本番の判断基準はパッとみて4問解けそう
試験当日は、事前に決めていた科目をそのまま選ぶ人もいれば、実際に問題を見て「予定を変更する人」もけっこういます。
国家一般職は、16科目の中から8科目を選択して解く方式。
つまり、本番での判断力が点数に直結。
基本のルールはシンプル。
👉 パッと問題を見て「5問中4問解けそうなら選択」「3問なら保留」「2問なら回避」
これを基準にすれば大きく外すことはありません。



各科目4問解ければ、全部で32問解けることになるので、大体どこの地域もボーダーを超えることができます。



問題をざっと眺めて、「見たことある・過去問で似た問題を解いた」感覚があれば、それは「解ける」サインだね
想定外に難化したときはどうする?



選ぶ予定だった科目が全然わからない…!
みたいなケースも普通にあります。
そんなときのためにも、代替科目を準備しておきましょう。
たとえば僕の年は、マクロが予想外に難しくて、本番では代わりに「財政学・経済事情」を選びました。



「保険科目」を持っておくのが安定感のコツです!



本番で選ぶ8科目+予備2科目=計10科目を候補にしておくと安心だね
まとめ|国家一般職の専門科目は「賢く選ぶ」のが合格のカギ
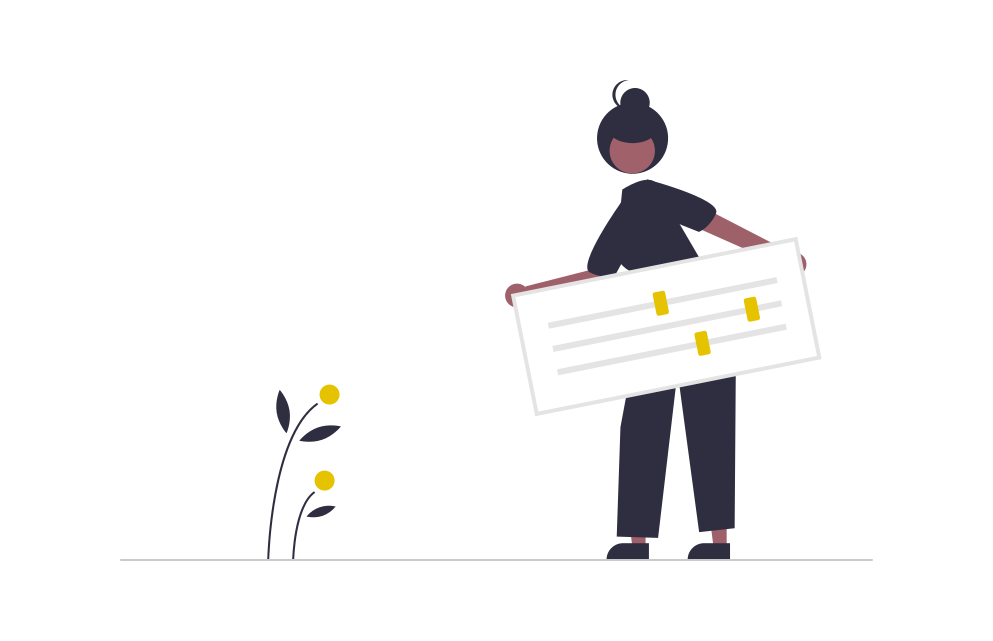
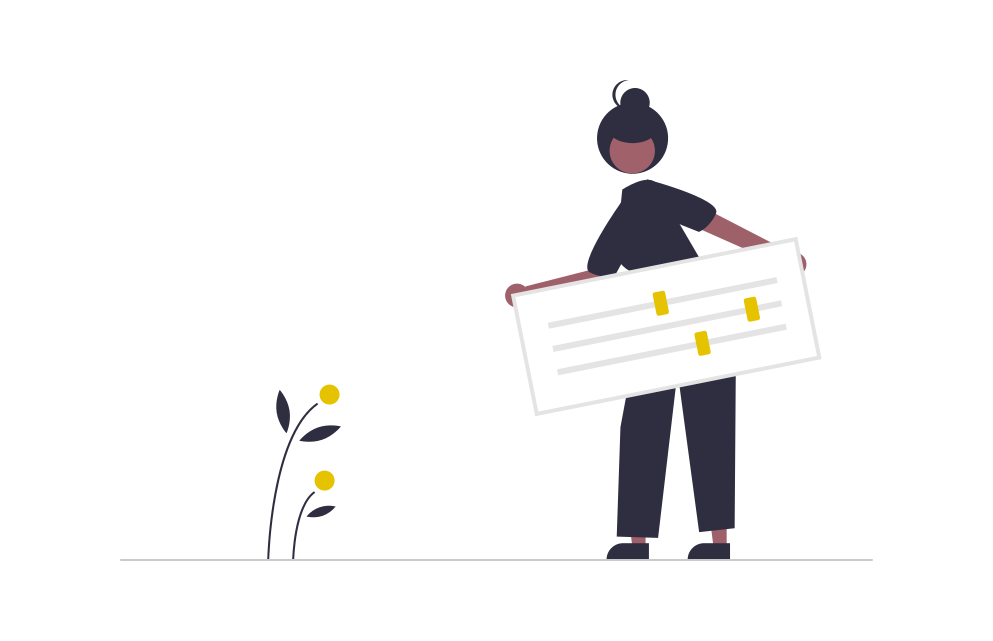
今回は「国家一般職の専門科目はどれを選ぶべきか?」について解説しました。
ここまでの内容をサクッと振り返ると👇
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 🎯 まず選ぶべき定番科目 | 憲法・行政法・ミクロ→ 安定して得点でき、併願にも強い! |
| ⚙️ 得点源にできる準主力科目 | マクロ・民法・財政学 → 理解中心で伸びやすく、点に直結する |
| 📚 中堅どころの選択可能科目 | 行政学/社会学・教育学/心理学 ・英語(基礎)→ 暗記が得意なら得点源にもなる |
| ⚠️ 年度によって難易度が高くなる地雷科目 | 政治学・国際関係・経営学・英語(一般) → 難化リスク・効率が悪い |
| 🧭 科目選びの判断基準 | 難易度・コスパ・汎用性を軸に、自分が「安定して得点できる科目」を選ぶ |
この記事が、あなたの科目選びの迷いを少しでも減らせたなら嬉しいです。
あとは淡々と積み上げていくだけです💪✨
💡 次に読むおすすめ記事




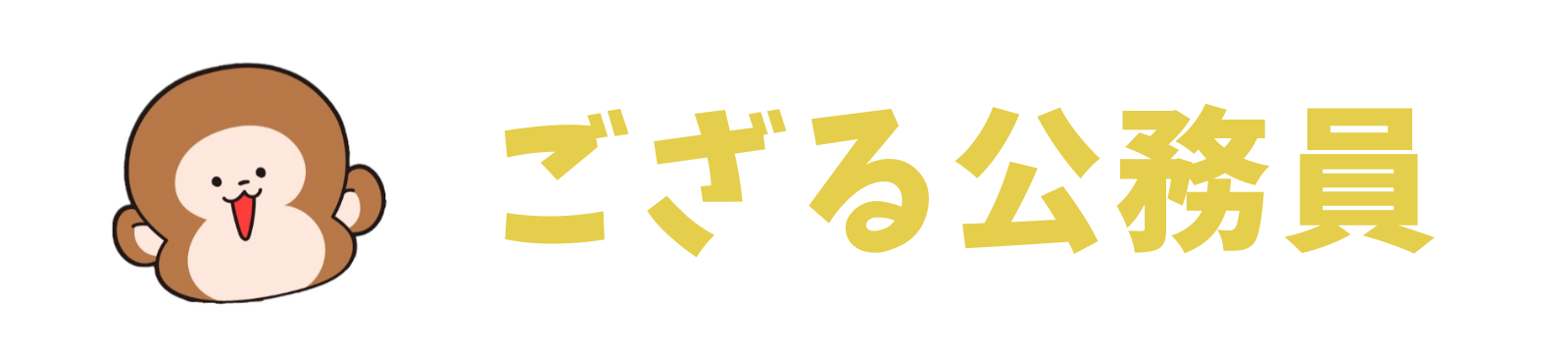




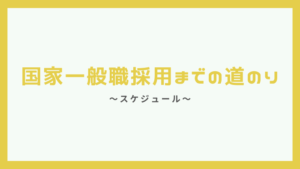



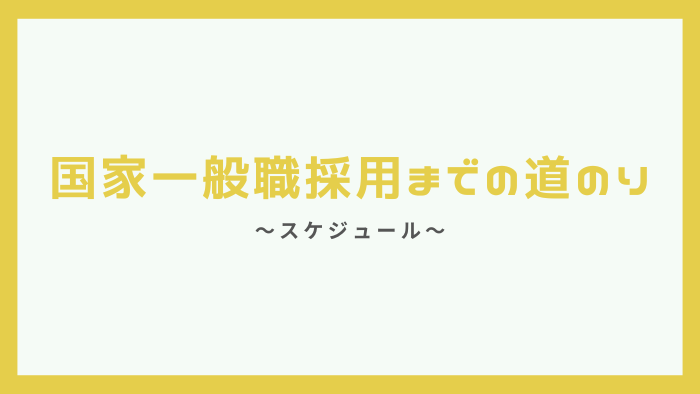
コメント