 ござる
ござるこんにちは、ござるです。
公務員試験の専門科目、多すぎて「どれを捨てればいいの…?」と悩んでいませんか?
実際、数十科目もある中ですべて完璧に仕上げるのはほぼ不可能。
合格者の多くは「捨て科目」を決めて、限られた時間を得点源に集中させています。
この記事では、
- 出題数と得点効率から見た「捨ててもOKな科目」
- 絶対に捨ててはいけない“主要5科目”
- 自分に合った取捨選択のコツ
をわかりやすくまとめました。
先に結論を知りたい人も、判断に迷っている人も、
この記事を読めば「どの科目に時間を使うべきか」が明確になります。



それでは、捨ててもOKな科目から見ていきましょう👇
結論|公務員試験の専門科目で捨ててもOKな科目一覧
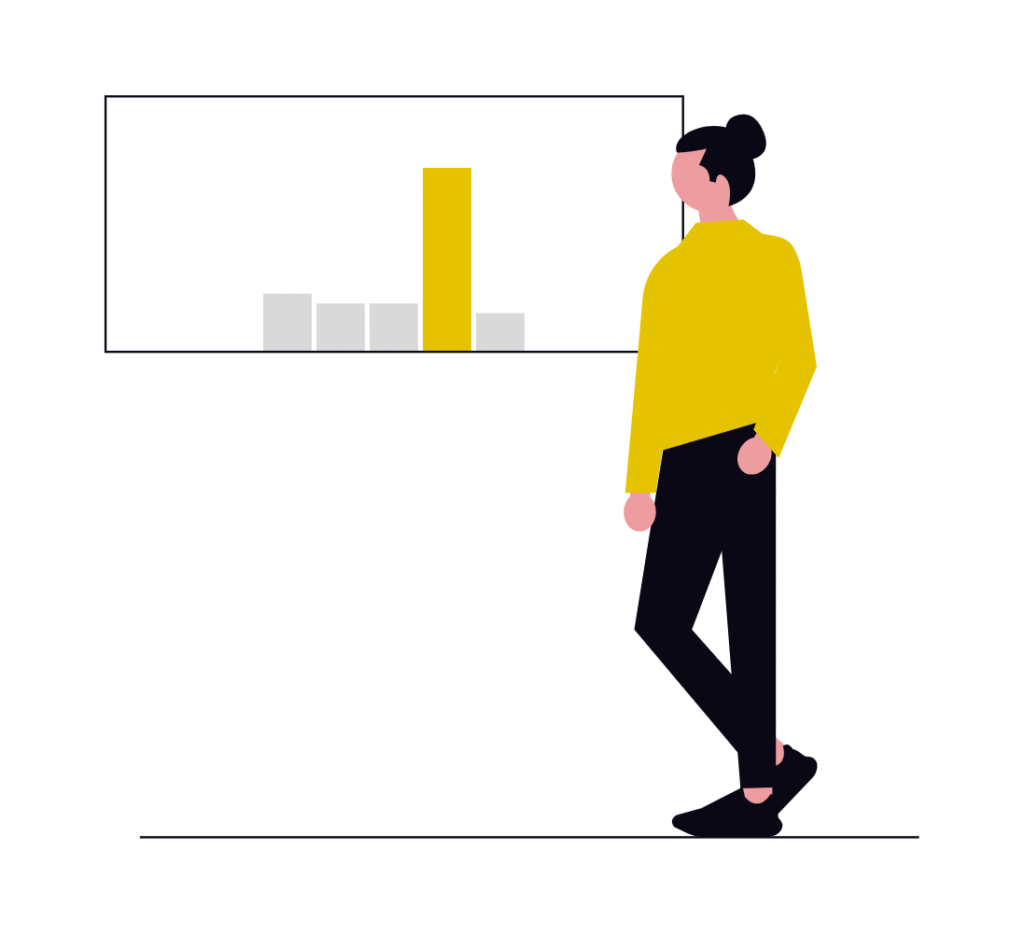
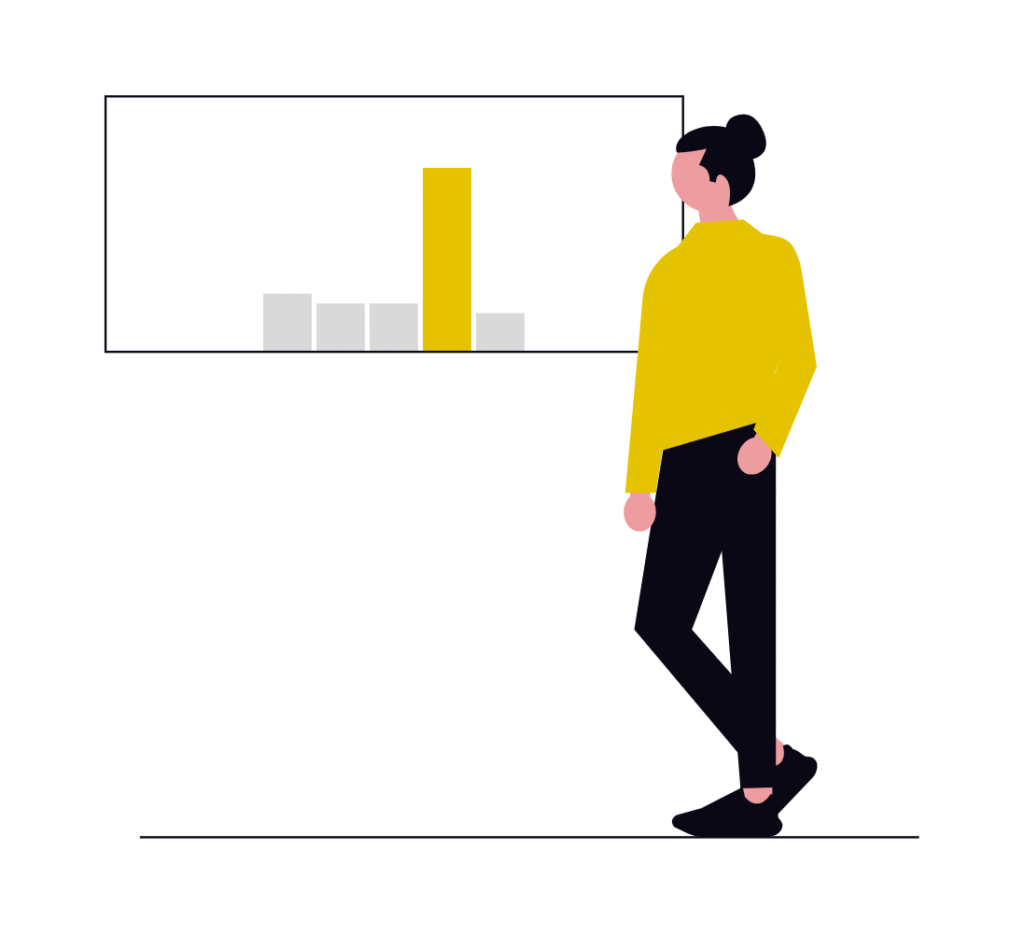
公務員試験の専門科目で「捨ててもOK」なのは、出題数が少なく、得点効率が悪い科目です。
一方で、出題数が多く配点も高い「主要5科目」は絶対に捨ててはいけません。
📊【試験別】捨ててもOKな科目一覧
| 試験タイプ | 捨ててもOK(または選ばなくてOK)な科目 | 理由・特徴 |
|---|---|---|
| 地方上級・市役所 | 刑法・労働法・経営学 | 出題2問前後+難易度高めで得点効率が悪い。最初に切る候補。 |
| 国家一般職(選択方式) | 政治学・国際関係・経営学・英語(一般) | 難易度・コスパを考えると、非効率で選ばない方が無難。 |
| どの試験でもNG(=捨て厳禁) | 憲法・行政法・民法・ミクロ経済学・マクロ経済学 | 出題数が多く、合否に直結する主要5科目。ここは必ず得点源に。 |



“どれをやるか”より、 “どれをやらないか”を決める方が早いよ!
🧭 ポイント整理
- 「出題数×難易度×関連性」で見極めるのがコツ。
- 出題数2問以下の科目は原則“切り候補”。
- ただし、**得点源を確保したうえでの“戦略的な捨て”**が前提。



次の章では、主要な試験ごとに、「どの科目が実際に“コスパが悪い”のか」を具体的に見ていきましょう👇
出題数から見た「捨て科目」候補まとめ【試験別】
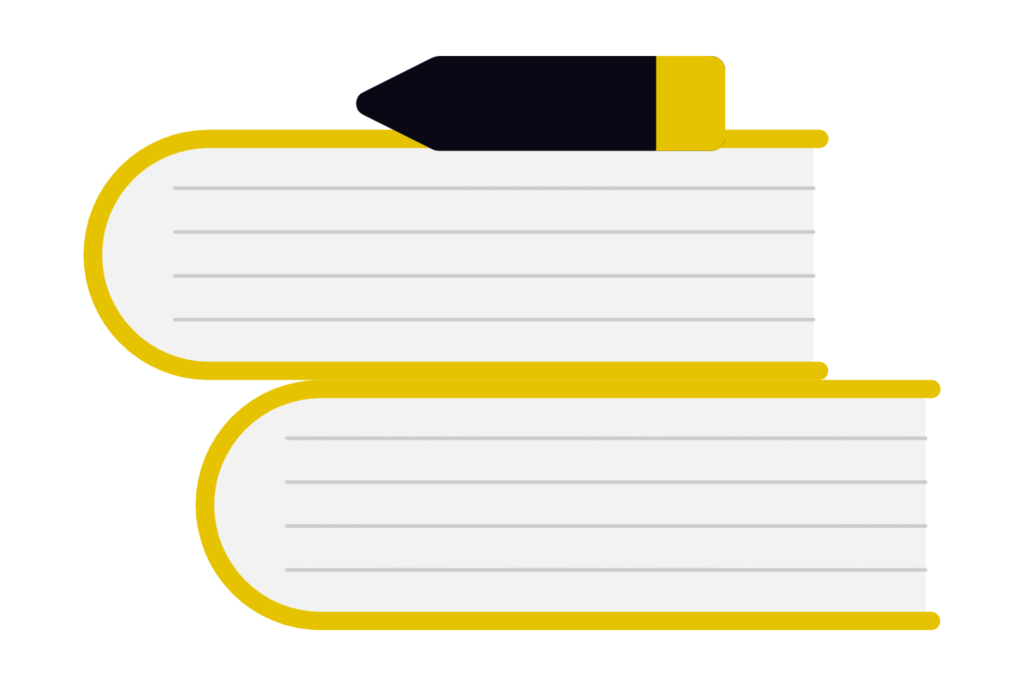
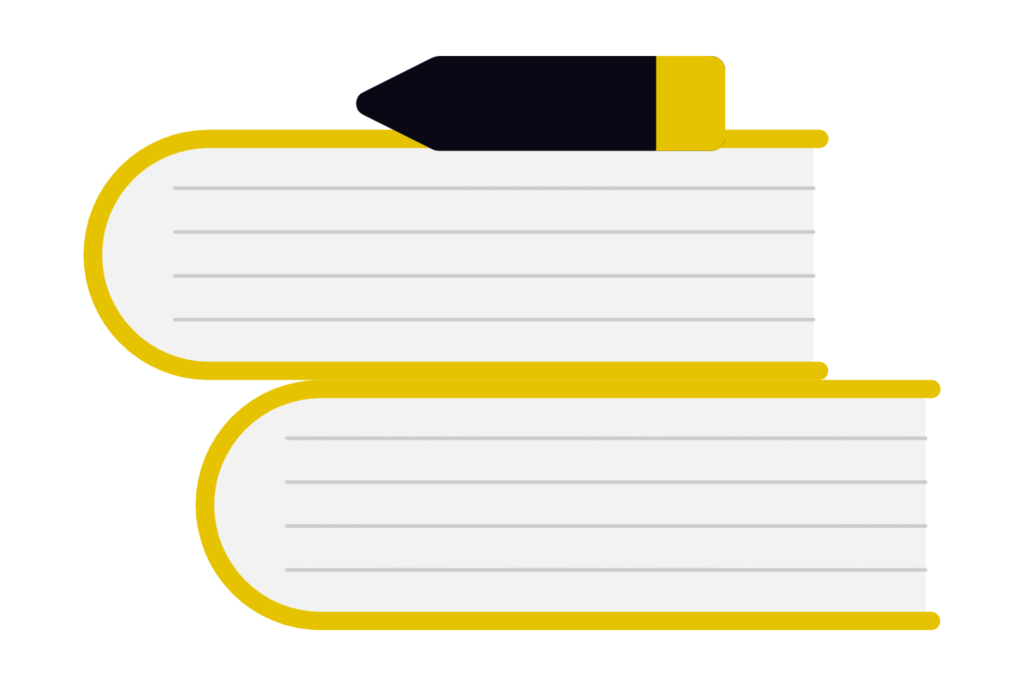
🟦 地方上級・市役所志望向け
地方上級・市役所では、出題数が多い「主要5科目(憲法・行政法・民法・ミクロ・マクロ)」に時間をかけるのが鉄則。
一方で、出題数が2問前後の科目は、得点効率が悪く“切る勇気”が必要です。
| 捨て科目 | 理由 | 補足 |
|---|---|---|
| 刑法 | 出題数が2問前後で内容が難しい | 時間があれば軽く触れる程度でOK |
| 労働法 | 出題2問・配点低め | 難易度は難しくないので、捨てないのもアリ |
| 経営学 | 出題数が少なく、年度差が大きい | 労力に対してリターンが小さい。地雷寄り科目。 |



合格を目指すなら、切る勇気も大事!
📌ポイント
- 出題2問前後の科目は“努力が点に直結しづらい”。
- 「行政法・民法・経済学系」に集中した方が合格効率が高い。
- 労働法は難易度が低めなので、余裕があるなら拾ってOK。
💡 補足:行政系科目(政治学・行政学・社会政策・国際関係)について
政治学や行政学などの行政系科目は、地方上級(全国型)でも出題数が2問前後。
これらはいずれも出題数こそ少ないものの、「まるごとパスワードneo2」など1冊で4科目まとめて対策できるため、完全に捨て科目にする必要はないです。
地方上級・市役所志望なら、この行政系セットは残しておくのが◎。



“まとめてやる”と意外と効率いいんだ!
🟩 国家一般職向け
国家一般職では、16科目中から8科目を選択して解答します。
そのため、 “捨てる”というよりも、最初から「選ばない科目」を決める戦略が重要です。
以下の4科目は、出題傾向や難易度・コスパを考えると、非効率で選ばない方が無難です👇
| 捨て科目 | 理由 | 備考 |
|---|---|---|
| 政治学 | 範囲が広く、年度によって出題傾向が大きく変わる | 「理論・思想・制度・時事」など出題領域が膨大。安定して得点しにくい。 |
| 国際関係 | 年ごとのテーマ差が激しく、当たり外れが大きい | 「外交史・国際政治・条約」など幅広く、時事要素も強い。 |
| 経営学 | 問題がマニアックで難易度が高め | 経営理論やマーケティングなど専門性が高く、学部知識がないと非効率。 |
| 英語(一般) | 難易度が非常に高く、上級者向け | TOEIC800点レベルでないと太刀打ちできない。英語が得意でも安定しにくい。 |
さらに詳しい解説は【保存版】国家一般職の専門科目はコレを選べ!おすすめ科目ランキングの記事でしています。
📌ポイント
- どの科目も出題内容や難易度が安定しておらず、得点効率が悪い。
- 「憲法・行政法・民法・ミクロ経済学・マクロ経済学・」などの鉄板科目に集中するほうが圧倒的にコスパがいい。
- 選択の自由がある分、「避ける判断」ができる人が合格に近づく。
逆に「絶対に捨ててはいけない」主要5科目


公務員試験の専門科目の中には、
「出題数が多く」「他試験でも共通」「得点安定性が高い」――
そんな“絶対に外せない”科目があります。
📊 絶対に捨ててはいけない主要5科目まとめ
| 科目 | 理由 | 一言コメント |
|---|---|---|
| 憲法 | すべての公務員試験で頻出。基礎理解が他科目にも波及。 | まず最初に仕上げたい王道科目。 |
| 行政法 | 法律系の得点源。地方上級・国家一般職・市役所すべてで出題。 | 憲法とセットで学習が基本。 |
| 民法(Ⅰ・Ⅱ) | 範囲は広いが、覚えれば安定して得点できる。 | 「しんどいけど結果に直結する」典型。 |
| ミクロ経済学 | 出題数・配点が高く、得点差がつきやすい。 | 理解重視で伸びる“コスパ良い科目”。 |
| マクロ経済学 | 出題パターンが安定。ミクロとセットで点が取りやすい。 | 理解が深まるほど得点が安定する。 |
💡 どう勉強に組み込むべきか
この5科目は、全体の勉強時間の6〜7割を占めてもOK。
なぜなら、
- 出題数が多く
- 他の試験にも使い回せて
- 得点配分も大きい



つまり、“合格点の土台”はこの5つで作れる。
🧩 補足:勉強順序の目安(例)
1️⃣ 憲法 → 2️⃣ 行政法 → 3️⃣ ミクロ経済 → 4️⃣ マクロ経済 → 5️⃣ 民法
この順に進めると、理解が繋がって無駄がない。
まずは“王道5科目”でラインを作ろう!
なぜ「捨て科目」を決める必要があるのか?


🧠 理由①:科目数が多すぎて、全科目対策は現実的じゃない
公務員試験の専門科目は、国家一般職なら16科目、地方上級でも10科目前後。
すべてに手を出すと、勉強時間が分散して伸び悩むのが現実です。
限られた時間の中で合格点を取るには、「やる科目」より「やらない科目」を決める方が重要。
苦手科目を無理に克服するより、
得意科目で確実に得点する方が効率も精神的負担も圧倒的に軽いです。



“全部やる”より、 “上手く削ろう”!
⚙️ 理由②:出題数と配点のバランスが悪い科目がある
出題数が2問しかないのに、何十時間も勉強するのはコスパが悪すぎます。
その時間を「行政法」や「経済学系」に回せば、同じ努力量で何倍も点が取れるんです。
つまり、 “出題数が少ない科目を切る=得点効率を最大化する”戦略。



この考え方を持つだけで、学習スケジュールがシンプルになります。
⏳ 理由③:精神的な負担を減らして、集中力を維持できる
科目を削る=迷いを減らすこと。
「これはやらない」と決めると、残りの科目に全集中できるようになります。
毎日の勉強で“やるべきリスト”が明確になるので、焦りや不安が減り、継続力も上がるんです。



捨てるって、実は“集中する”ための最強スキルなんだ!
🧭 まとめ:捨てることは「逃げ」じゃなく「戦略」
科目を捨てる=サボりではなく、合格に近づくための選択と集中。



出題数・得点効率・自分の得意分野を見極めて、「限られた時間で最大の結果を出す」ことこそが、公務員試験の本質です。
「捨て科目」を決める3つの判断基準
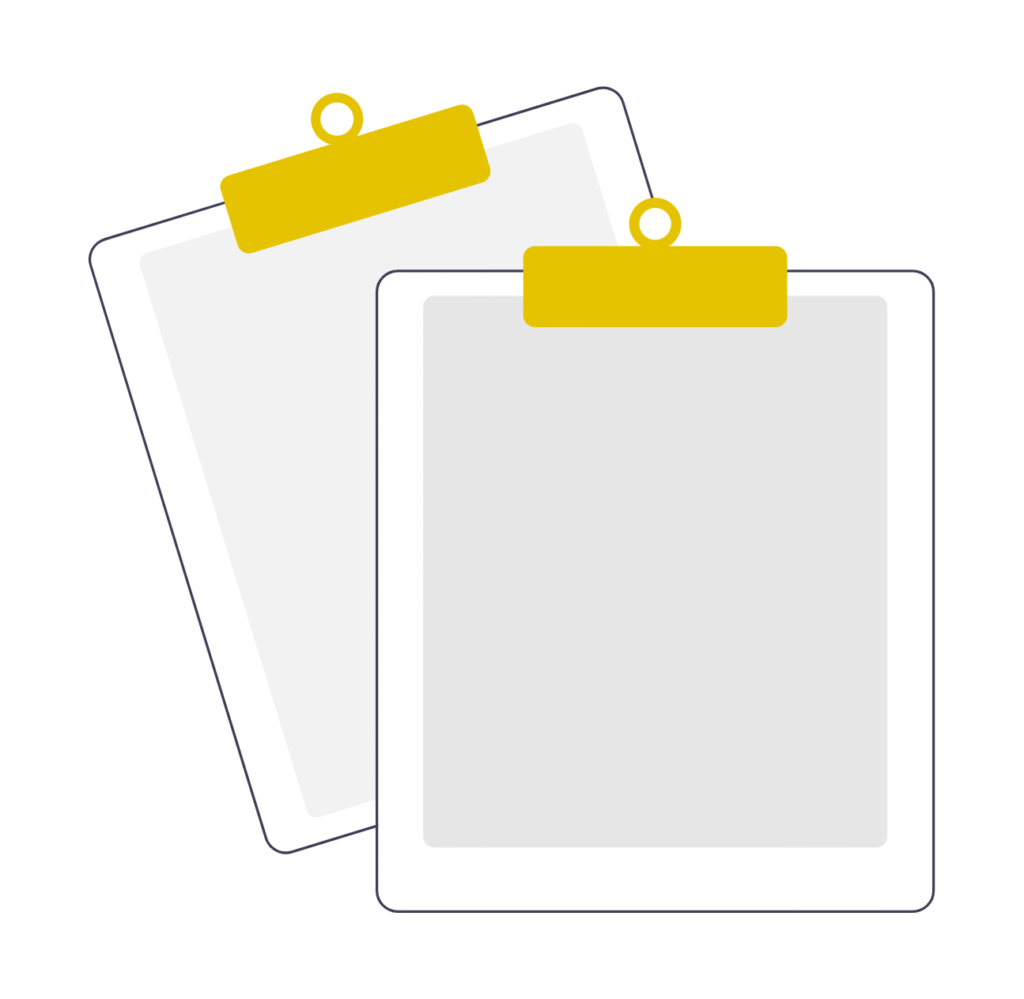
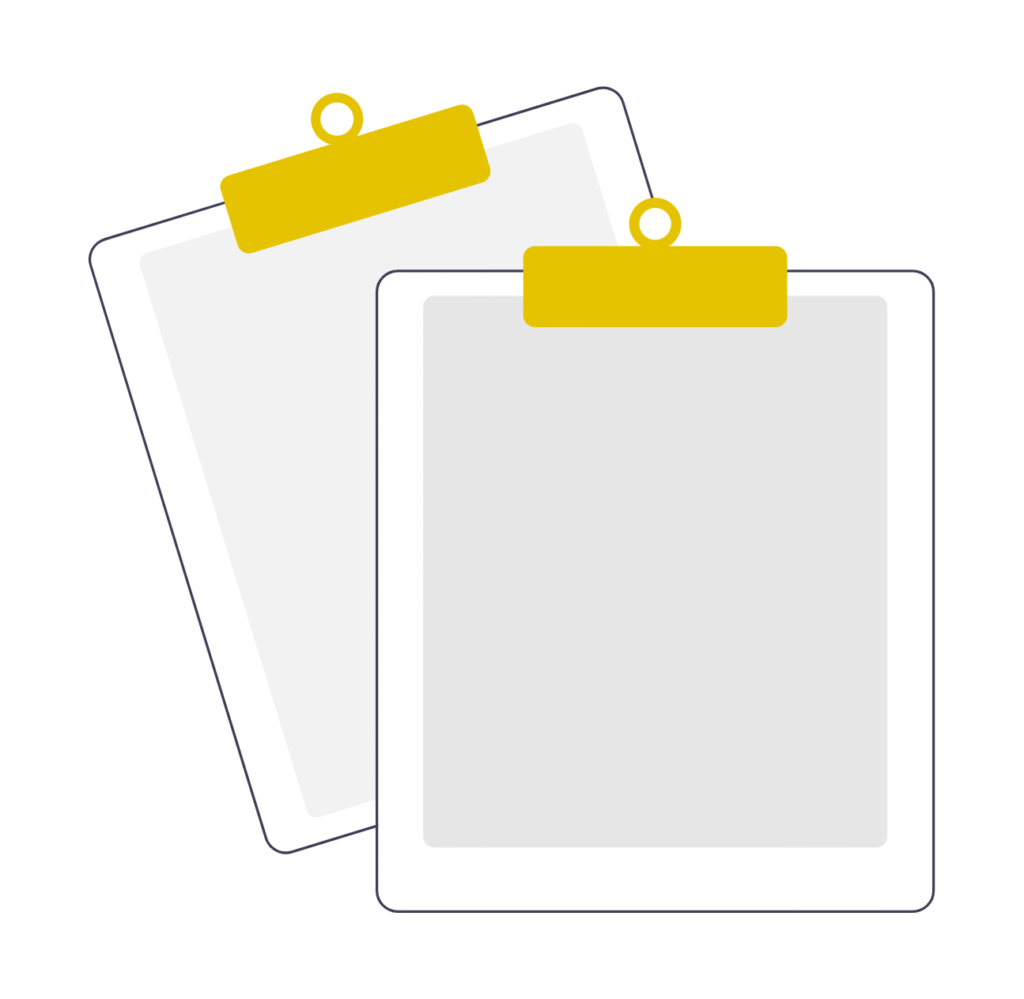
「捨てる勇気が大事なのは分かったけど、どうやって判断すればいいの?」
ここでは、誰でも迷わず判断できるように、3つの基準にまとめました👇
✅① 出題数が少ない科目は思い切って切る
出題数が2問前後しかない科目は、得点効率が悪い典型です。
刑法・労働法・経営学などがその代表。
2問のために何十時間も勉強するより、5問出る「行政法」や「経済学」に集中した方が、同じ時間で2〜3倍の得点が取れる可能性があります。
ただし例外として、「財政学」は出題数こそ少なめですが、経済学との関連が強く、他試験でも出題されやすいため“残す価値あり”の科目です。



“出ない科目”に時間をかけるのは、ムダ!
✅ ② コスパ(得点効率)が悪い科目は避ける
“範囲が広いのに出題が少ない科目”や、
“努力しても点が安定しない科目”は、思い切って捨てる対象。
例えば国家一般職の「政治学」「国際関係」「経営学」などは、年度差が大きく、安定して得点しにくい地雷科目です。
👉「努力が点に直結するか?」で判断するのがポイント。
✅ ③ 他試験との関連性(汎用性)が低い科目は後回し
「1試験のみで、他では使えない」科目は効率が悪いです。
たとえば「教育学」「心理学」は、国家一般職以外では出番がほぼありません。
逆に、「財政学」や「経済学」は複数試験で共通して出題され、他科目との関連も強いので残すべき科目です。



“一石二鳥”にならない科目は後回しでOK!
💡 まとめ| “伸びる科目に投資する”のが鉄則
捨て科目を決めるときは、
出題数 × 得点効率 × 汎用性
この3つの掛け合わせで考えるのがベスト。
どれも低いなら、その科目は“切る候補”です。
逆に、3つ揃って高い科目は伸びしろが大きい得点源になります。



時間は有限。伸びる科目に全振りして勝とう!
まとめ|「捨てる勇気」が合格を近づける
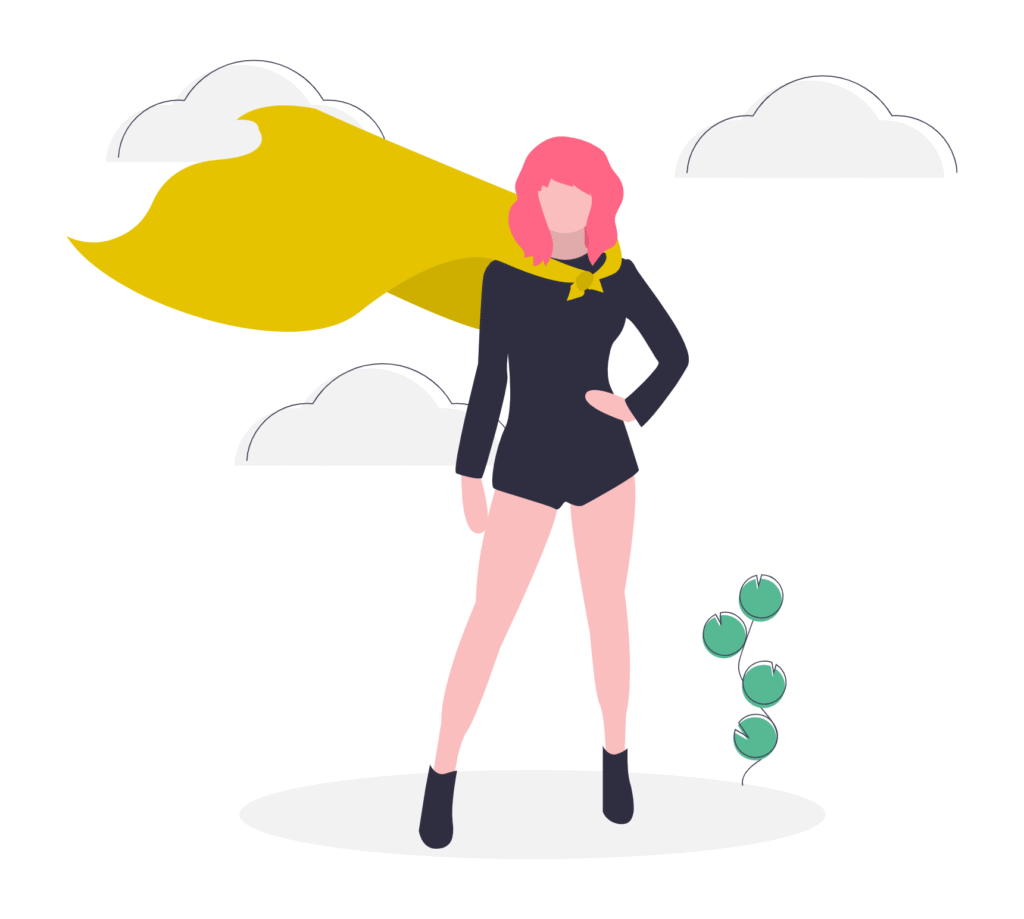
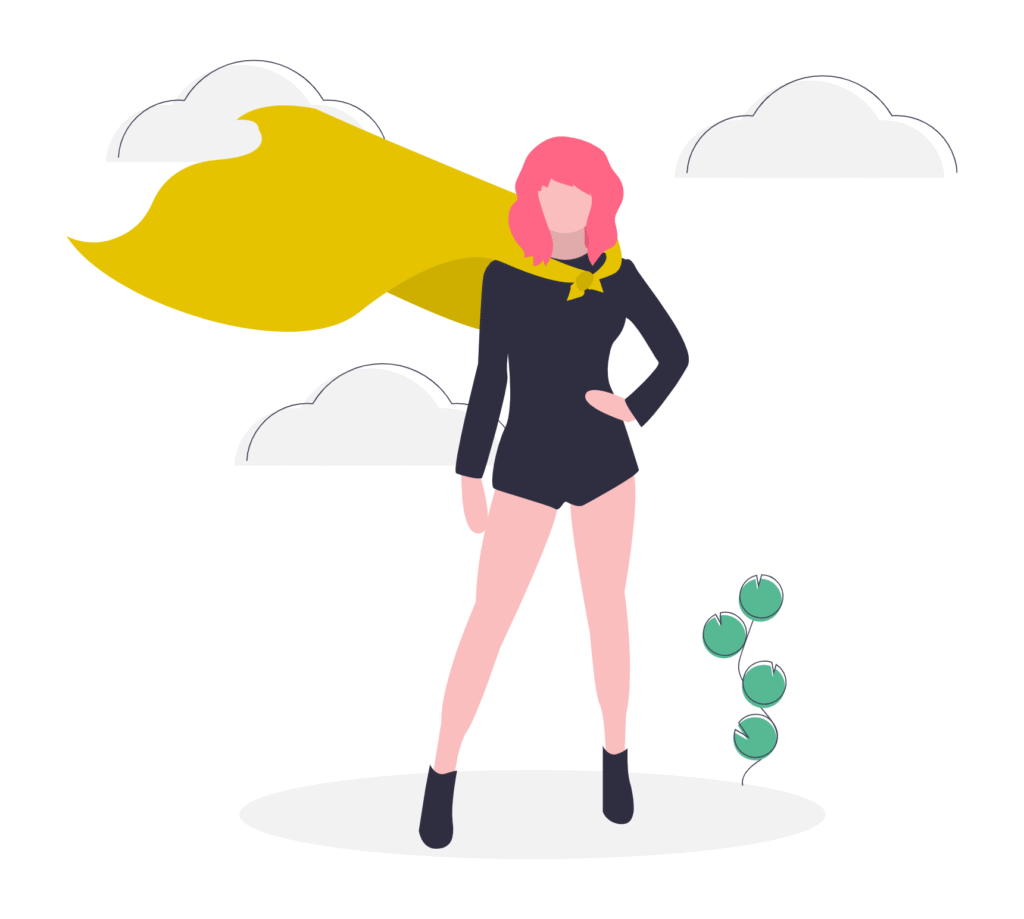
公務員試験は、すべてを完璧にやろうとすると落とし穴にハマります。
大事なのは「やる勇気」よりも「やらない勇気」。
出題数が少なくコスパの悪い科目は切って、得点源に集中しましょう。



捨てる=手を抜くことじゃなく、合格への最短ルート!
💡次に読むおすすめ記事






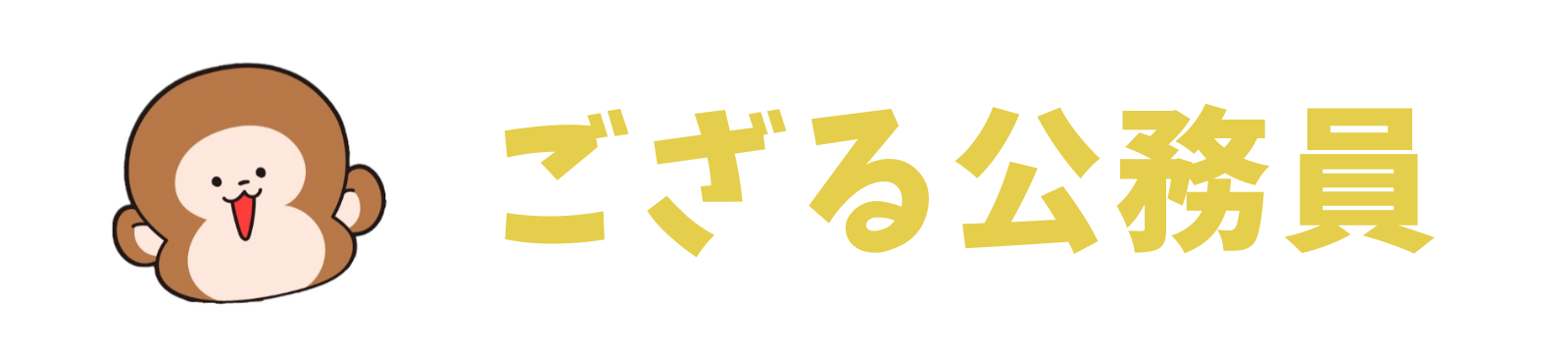




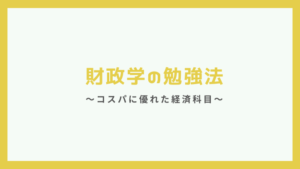
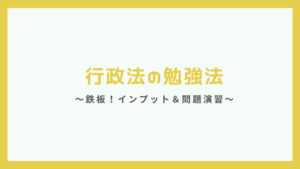




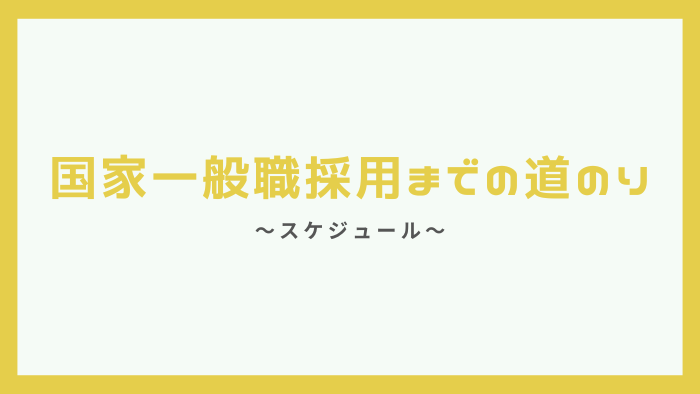
コメント