 ござる
ござるこんにちは。ござるです。
公務員試験の受験生の皆さん!
試験勉強をしようと思っても、何から手を付けたら良いかわからなくないですか?
そうなんです!公務員試験は科目が多いので、勉強する順番がわかりづらいんですよね。
しかし、公務員試験でも、効率的に勉強する順番は存在します。
そこで、今回は、これから公務員試験の勉強を始める受験生に向けて、「何から勉強を始めるべきか」を解説していきたいと思います。
まず、いきなり結論から言うと、「数的処理」から勉強を始めてください。
公務員試験の勉強は「数的処理」から





「数的処理」ってなんだ!?
と思う人もいると思うので解説すると
公務員試験では「数的処理」という「公務員としての事務処理能力が問われる」科目が出題されます。
「数的処理」は、さらに「数的推理」「判断推理」「資料解釈」に分けることができますが、全体で共通して言えることは、主に中学・高校の数学的知識と関連して、思考力や推理力を問う問題が出題されます。



うーん。自分は数学が苦手だから出来るか不安・・・
と思う人は出来るだけ早く勉強を始めたほうが良いと思います。
というのも「教養科目」の大半を「数的処理」が占めているんです。
例えば、2024年から変更になった「国家一般職」の教養科目は、「数的処理」が47%も占めています。
つまり、避けては通れない重要科目であり、いち早く勉強に取り掛かることが重要なんですね。
「数的処理」を始める時期:試験1年前から~
というわけで、「数的処理」から勉強を始めるのがオススメなんですが、始める時期としては試験1年前ぐらいが目安かなと。
筆者は「数的処理」だけ1年以上前から勉強を始めていたのですが、正直あまりアドバンテージは感じませんでした。



結局早く勉強しても忘れてしまうので、1年前ぐらいがベストなのではないかと思います。1年あれば十分成績は伸ばせますよ。
「数的処理」の勉強方法:理解用参考書を3周する→スーパー過去問ゼミで過去問演習
「数的処理」の勉強は、まず「理解用参考書」で解法を学びましょう!
「数的処理」はある程度決まったパターンの問題が出題されるので、「理解用参考書」で「解法のパターン」を覚えることが重要です。
「数的処理」の「理解用参考書」は色々ありますが、「畑中敦子先生」が書いている参考書は、どれも解説が丁寧でわかりやくいので、オススメです。(畑中先生シリーズならなんでも良いと思います。)



数学が苦手な僕でも理解することが出来たよ!
そして、理解用参考書でインプットが終わったら、「スーパー過去問ゼミ」で、ガンガン問題演習しちゃってください。
結局のところ、「数的処理」は、問題演習で数こなすことが大切なので、インプットが終わったら、早めに演習に移りたいですね。
では、ここからは、「数的処理」の次に勉強したい科目について解説していきます。
「数的処理」の次に取り組みたい科目


「数的処理」の勉強を始めたとして、次に取り組みたい科目なんですが、4科目あります。
ズバリ「憲法」「行政法」「民法」「ミクロ・マクロ経済学」です。
なぜこの4科目かというと「出題数が多い重要科目だから」ですね。
「数的処理」と合わせて「主要5科目」と言ったりするぐらいなので、これらは「公務員試験」の勉強の中心であり、優先して勉強する必要があります。



とりあえず、勉強を始めた受験生の皆さんは、「この5科目を中心に勉強を始めるんだ」ということを頭に入れておいてほしいです。
憲法
「憲法」は、内容も馴染み深く、理解しやすい科目なので、「数的処理」の次に勉強する科目としては一番オススメです。
学校の授業やニュースなどで耳にしたことのある条文が出てくるので、理解しやすいですね。
「憲法」はインプット参考書を3周程度すれば、知識が大体身につくと思います。
オススメの参考書は「寺本康之の憲法ザ・ベストハイパー」です。



迷ったら憲法からが良いと思う!
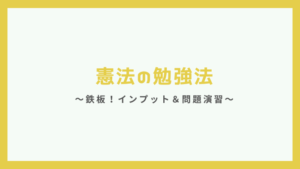
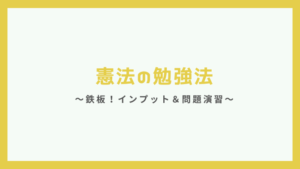
行政法
「行政法」は、受験生にとっては馴染みのないものなので、「憲法」と比べると、「理解しづらい」「覚えにくい」と感じる科目かもしれません。
なので、個人的には「憲法」を学習してから「行政法」に取り掛かるのが良いのかなと思っています。
ただ、結局は「暗記科目」で、参考書を何周もすれば自然と覚えられるので、あまり気にすることもないのかなと思ったり。
オススメのインプット参考書は「寺本康之の行政法ザ・ベストハイパー」です。
憲法と同じシリーズですが、ちゃんとわかりやすいです。



行政法は、気合で暗記しちゃいましょう!
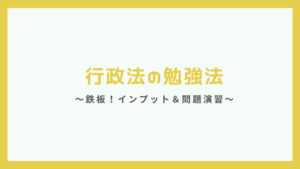
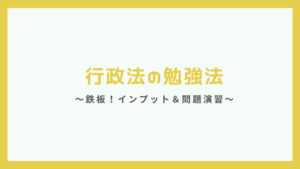
民法
「民法」は「勉強量の膨大さ」と「内容の複雑さ」から、苦手としている受験生が多い科目のひとつです。
「民法」を「捨て科目」にする受験生もいますが、重要科目には変わりないので、根気強く勉強した方が良いと思います。
「民法」も暗記科目なので、時間をかけて何度も復習すれば、最終的には覚えられます。



ただ、「憲法」「行政法」より先に勉強し始めてしまうと、挫折しかねないので、この2科目の勉強が終わったぐらいで始めるのがベストかなと思います。
オススメのインプット参考書は「寺本康之の民法ザ・ベストハイパーシリーズ」です。
何買えばわからない人は、このシリーズを買っておけば、間違いないです。
ミクロ経済学・マクロ経済学
ミクロ経済学・マクロ経済学も、公務員試験では問題数が多い重要科目なので、早めに勉強を始めるのべきでしょう。
「経済学」と聞くと、



数学が出来ないといけないのかな…
と不安に思うかもしれませんが、実際に使う知識は、連立方程式、微分、指数の計算ぐらいで、数学の知識はそこまで必要ありません。
大学受験で数学を勉強した人は、まず問題ないですし、高校で数学を勉強しなくなった人は、微分の知識ぐらいは勉強しておくと良いと思います。
難易度的には、ミクロよりマクロのほうが難しめなので、ミクロから取り掛かると挫折しにくいんじゃないかなって思います。


年内に主要5科目を仕上げる気持ちで!
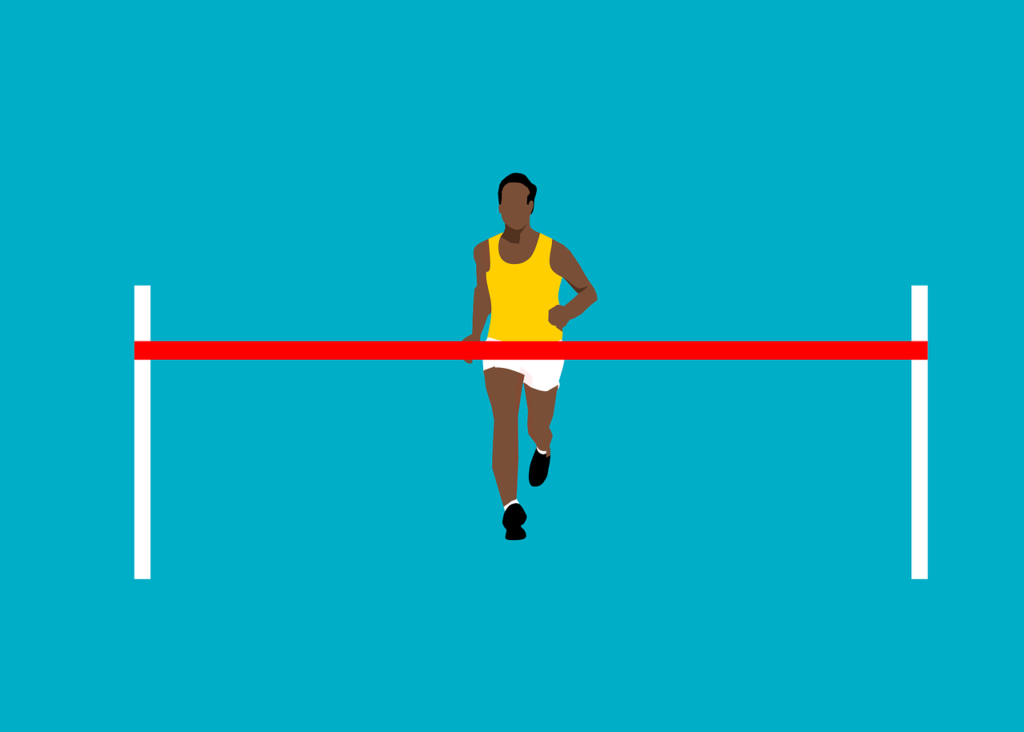
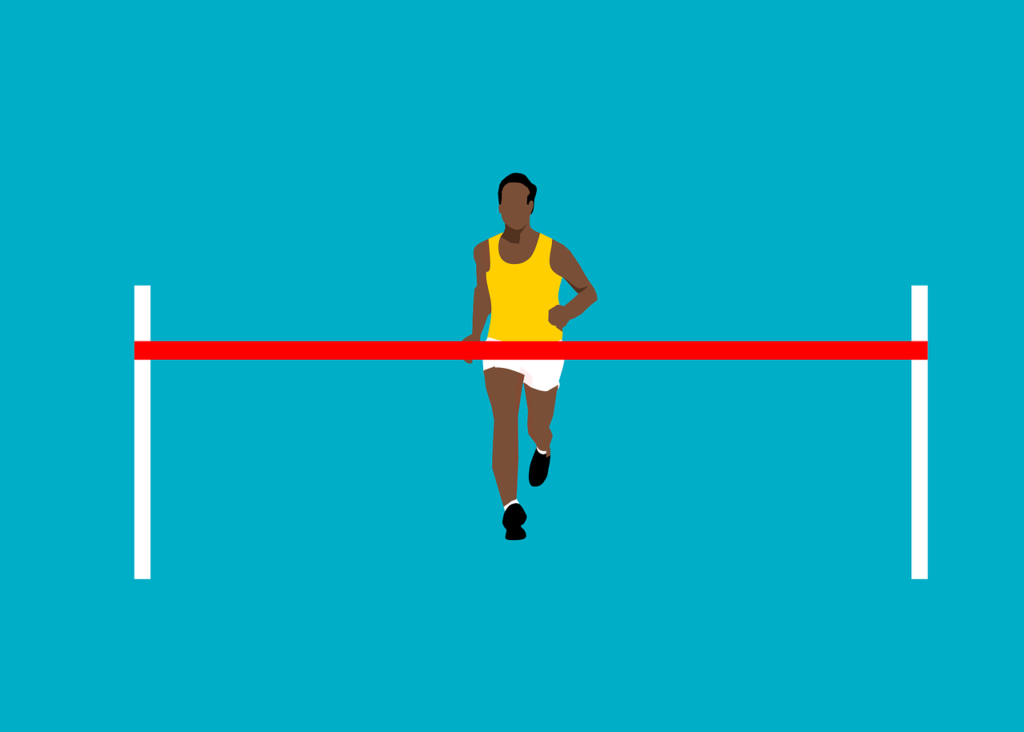
ではこの「数的処理、憲法、行政法、民法、ミクロ・マクロ経済学」をどのぐらいのペースで勉強すれば良いかと言うと
「年内に主要5科目のインプットは完璧に終えている状態」
ぐらいで行きたいですね。
・「数的処理」は、演習をこなして、解法のパターンを大体理解している
・「憲法・行政法・民法・ミクロ経済学・マクロ経済学」は、参考書でインプットを終えている
ぐらいが理想です。
ただ、勉強のスケジュールは予定通り行くわけではないので、遅れていても心配しなくて良いですし、ぶっちゃけ最後の直前期の追い込みでなんとかなったりします(笑)
ただ、勉強を始めた受験生には、一つの目安として「年内に主要5科目を仕上げる」ことを意識してスケジュールを組んでもらえれば、「順調な勉強計画」になるのかなと思います。


まとめ
- 公務員試験の勉強は「数的処理」から
- 数的処理」の次に取り組みたい科目は、「憲法」「行政法」「ミクロ経済学」「マクロ経済学」
- 年内に「主要5科目のインプットは完璧に終えている状態」を目指して頑張ろう!



最後まで読んでくれてありがとうございました!

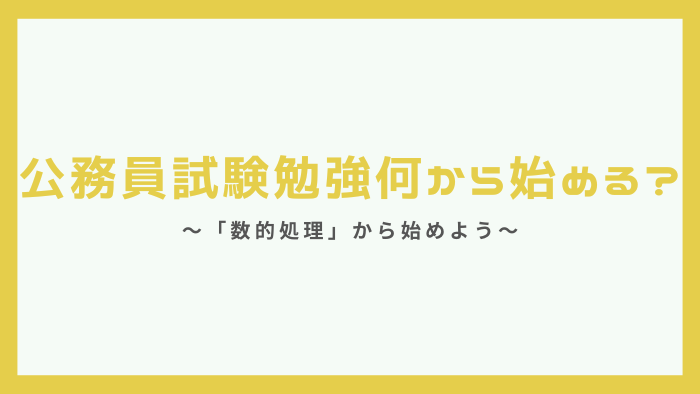









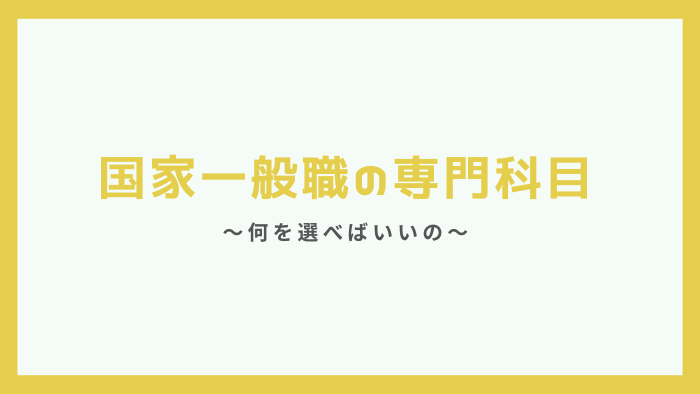
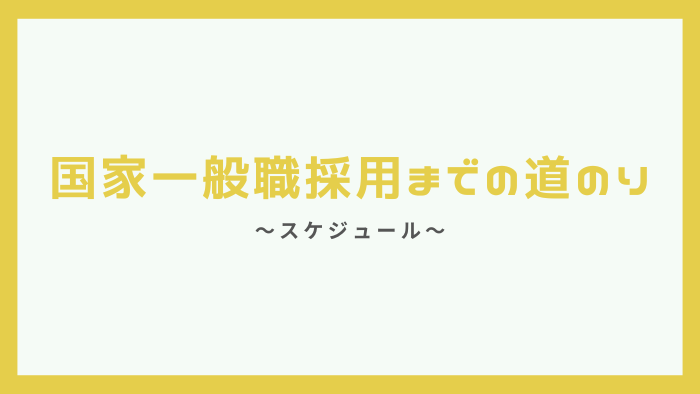
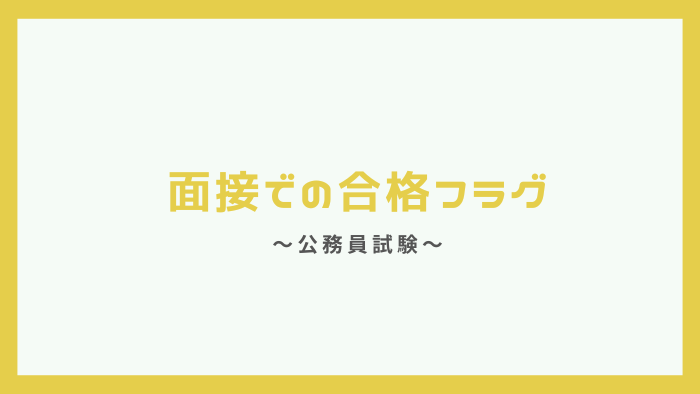
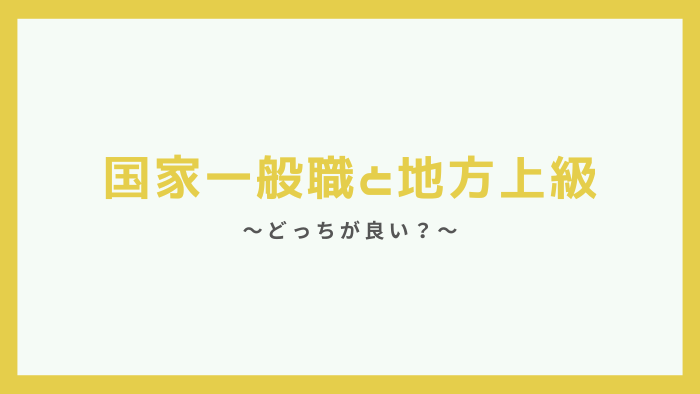
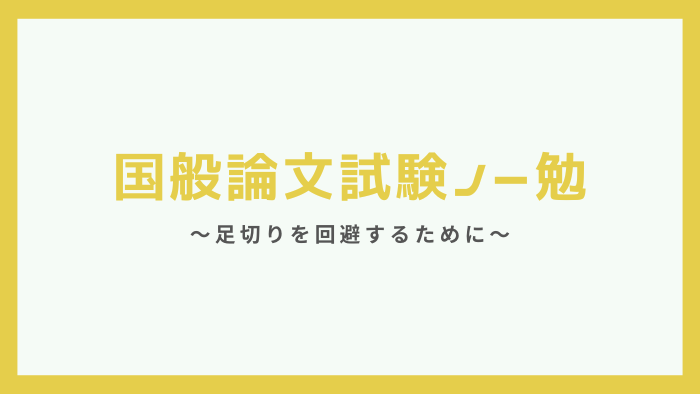
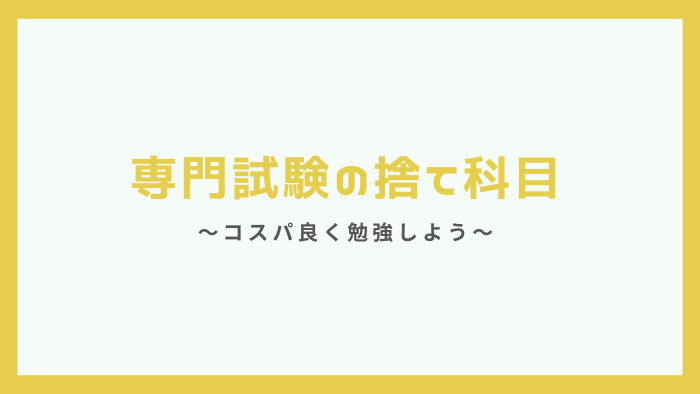






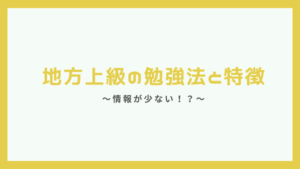
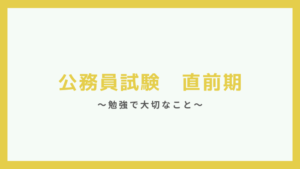
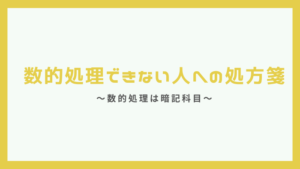
コメント