 ござる
ござるこんにちは。ござるです。
受験生の中には



公務員試験は可能な限り受けまくるぜー!
という戦略を考えている人もいると思います。
乱れ打ちのように受けまくる「数打ちゃ当たる戦法」ですね。
でも、これって本当に正しい戦略なのでしょうか!?
正直、気になりますよね。
なので、今回は、「公務員試験をとにかく受けまくるのは正しいのか?」について解説していきたいと思います。
参考になれば嬉しいです。
結論:「公務員試験をとにかく受けまくる」は基本的には正しい
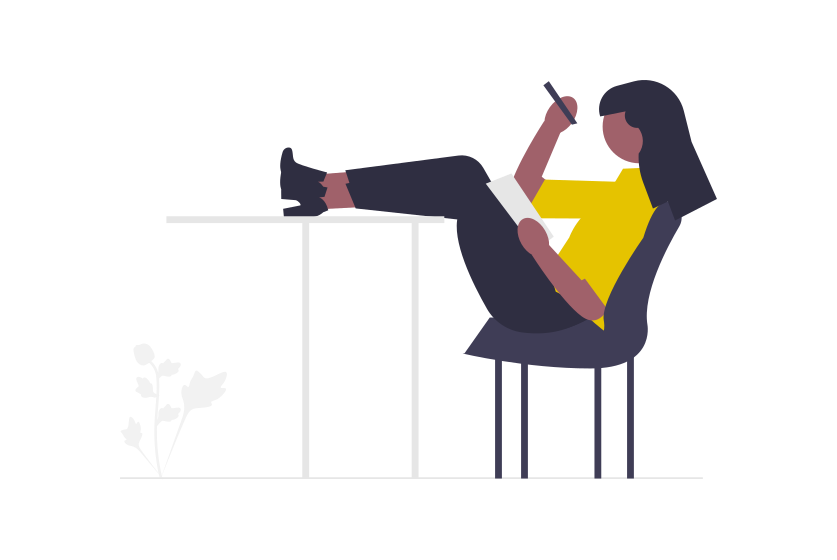
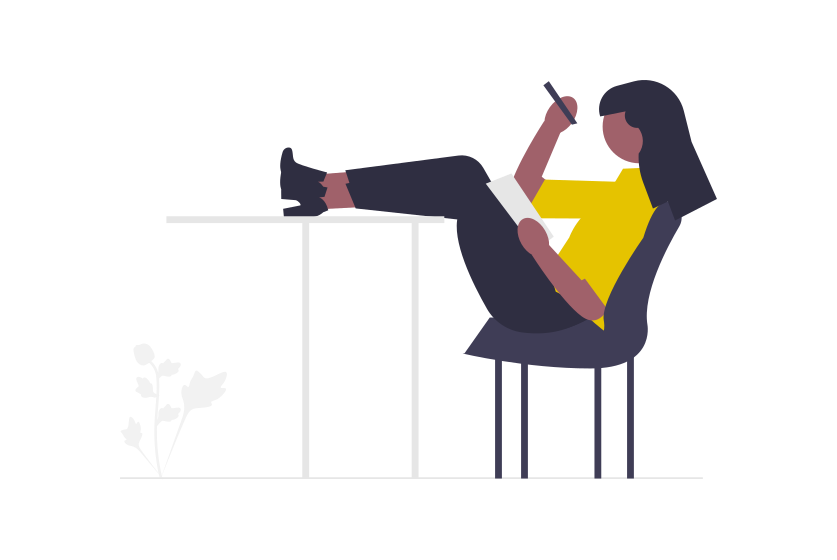
さっそく結論から言いますと
公務員試験をとにかく受けまくるのは基本的には正しい
です。間違っていません。
公務員試験は受験できるところが限られているため、可能な限り受験するというのがセオリーです。
民間企業の就活では、20社とか30社とか受けられますが、公務員はそうはいきませんからね。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
どんなに頑張っても10ぐらいが限界です…
元々併願できる数が少ないので、持ち駒を増やすというのは理にかなっています。
とにかく受けまくる戦略のメリット・デメリット
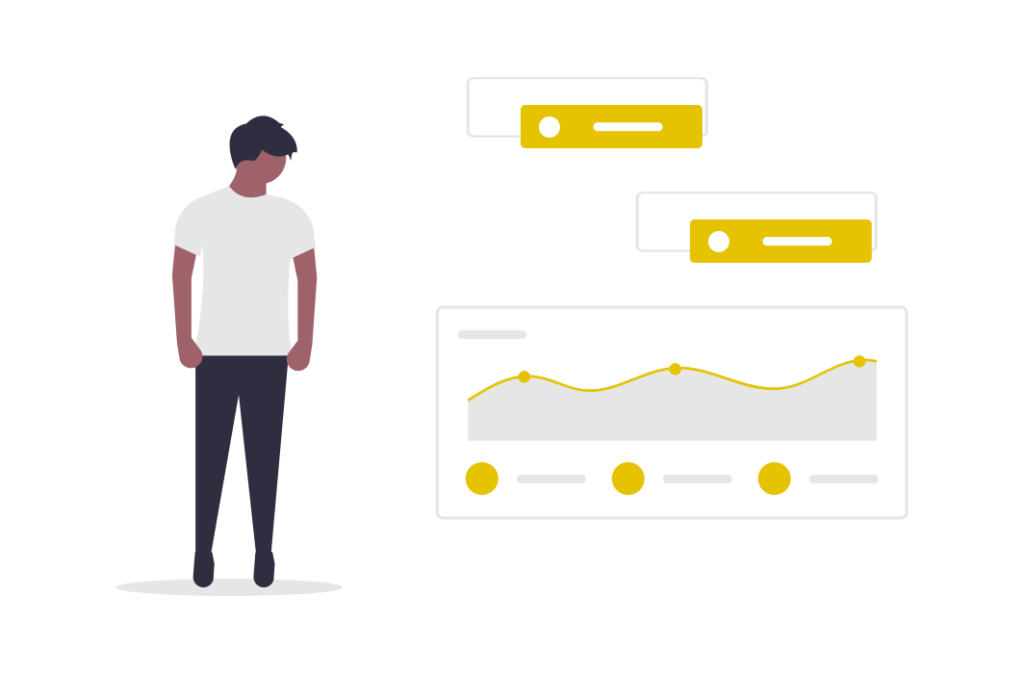
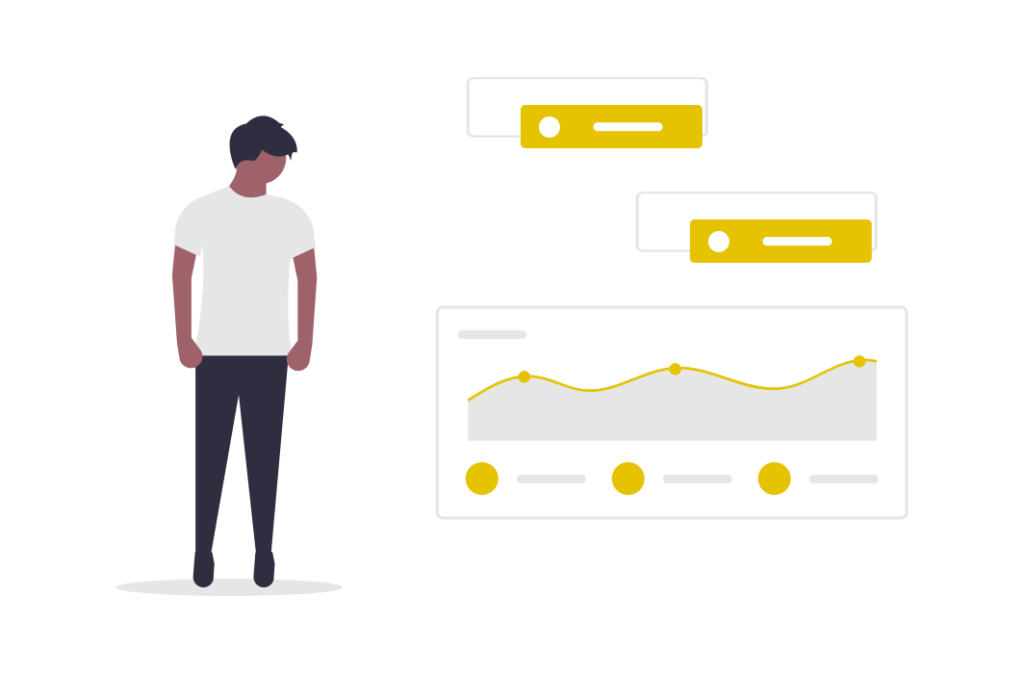
メリット1 全落ちする可能性を下げることができる
公務員は併願できる数が少ないので、中には「全落ち」してしまう人も珍しくありません。
「全落ち」する可能性を減らすためにも、持ち駒は増やしておきたいですよね。
「とにかく受けまくる戦略」は、持ち駒を増やすことができるので、理論上は公務員になれる確率を上げることができます。
仮に公務員試験の合格率が全て20%だったとすると
- 個受験→全落ち率80.0%
- 個受験→全落ち率64.0%
- 個受験→全落ち率51.2%
- 個受験→全落ち率40.96%
- 個受験→全落ち率32.77%
- 個受験→全落ち率26.21%
- 個受験→全落ち率20.97%
- 個受験→全落ち率16.78%
- 個受験→全落ち率13.42%
- 個受験→全落ち率10.74%
見てわかるように、併願数を増やすことで全落ち率は着実に減少します。
単純計算ですが、10個併願できれば、90%の確率で公務員になれるわけですね。
メリット2 本番の経験を積みながら成長できる
公務員試験に合格するためには、「試験本番」で力を発揮しなくてはいけません。
ですが、「試験本番」は独特な雰囲気と緊張感があります。
僕はそれほどメンタルが強くないので、最初に受けた筆記試験の本番はガチガチに緊張してしまって、正直6割ぐらいの出来でした。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
はあ…自分はなんてプレッシャーに弱いんだ…
と自己嫌悪しました。
しかし、次に受けた筆記試験では、なぜかあまり緊張せずに自分の力を発揮できたんです。
このとき「本番に慣れる」重要性に気づきました。
実際の試験環境に慣れることで、緊張感を克服し、自信をつけることができたんですね。
面接試験でも同じことが言えます。
併願先が多ければ、それだけ慣れるチャンスがあるわけなので、その分あとの試験に余裕が生まれます。
また、経験から学び、改善できるのもメリットです。
筆記試験であれば



この科目ができなかったからもっと勉強しよう!
とか
面接試験であれば



〇〇の質問に対する回答が上手くできなかったから次は修正しよう!
みたいな感じで次に生かすことができるわけですね。
なので、自分の「本命試験」よりも前に「滑り止めの試験」をいくつか受けておくのがオススメです。



へ~じゃあたくさん受けまくれば良いんだね~



でもちょっとまって!その分デメリットも存在するよ!
デメリット1 勉強や面接対策が中途半端になる可能性がある
何度も試験を受けるデメリットとして、勉強や面接対策が中途半端になる可能性があることが挙げられます。
試験日はまるごと1日潰れてしまいますし、労力を使うので、次の日に響いたりもするんですよね。
直前期は、集中して勉強したい時期ですが、色々な試験が入ってくることで、勉強リズムが崩れたりする可能性があります。
通常の勉強スケジュールより、1ヶ月・2ヶ月前に仕上げるつもりで取り組んでください。
複数の試験を受けられるだけの余裕を作りましょう。
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
-e1707016127242-150x150.png)
ギリギリな計画を立ててしまうと、この戦略は失敗しかねません…
デメリット2 絶対行きたいところがある人には不向き
とにかく受けまくる戦略は、どうしても行きたいところがある人にはあまりオススメしません。
そういう人は、無理のない併願数(3~5)にとどめて、絶対行きたいところの対策に注力したほうがいいです。



僕は、地元の市役所に入りたいと強く思っていたので、併願先を3つに絞りました。
- 地元の市役所(第一志望)
- 国家一般職
- 地元以外の市役所A
- 地元以外の市役所B
今思えば、少しリスキーな選択だったかもしれませんが、その分第一志望の対策はバッチリできたので、結果的には良かったかなと。
この辺の戦略は、「絶対行きたいところがある人」と「とりあえず公務員になりたい人」で変わってくると思うので、自分にあったほうを選んでみてください。
公務員試験をとにかく受けまくる人の併願パターン


最後に、とにかく受けまくる人の併願パターンを紹介します。
【2024年版】
3月17日(日) 国家総合職
4月21日(日) 特別区Ⅰ類
5月11日(土) 裁判所職員
5月12日(日) 東京都Ⅰ類A
5月26日(日) 国税専門官・財務専門官
6月2日(日) 国家一般職
6月16日(日) 地方上級・市役所A日程
7月7日(日) 国立大学法人
7月 市役所B日程
9月1日(日) 税務職員
9月 市役所C日程
こんな感じですね。
この他にも、自治体独自の試験方式もあったりするので、もう少し受けられると思います。



ただ、闇雲に増やしすぎるのもどうかと思うので、受けられる範囲で受験してみてください。
まとめ
今回は、「公務員試験を受けまくるのは正しいのか」について解説しました。
基本的には正しいとは言いましたが、デメリットもあるので、自分にあった戦略で挑んでみてほしいと思います。
いちばん重要なことは、試験の数を増やすことではなく、日々の勉強や面接対策をしっかりすることなので、そこだけは忘れないでほしいです。
以上になります。



最後まで読んでくれてありがとうございました!
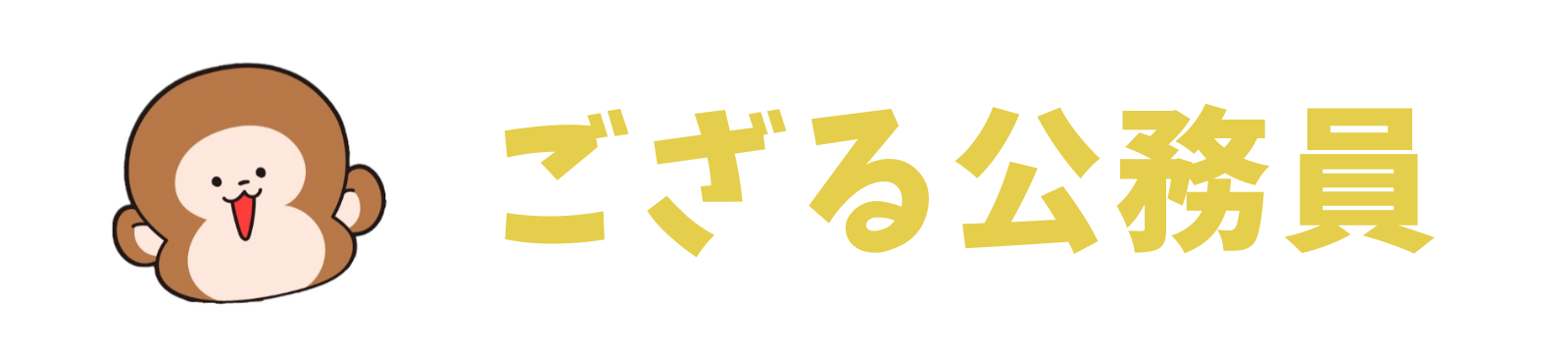








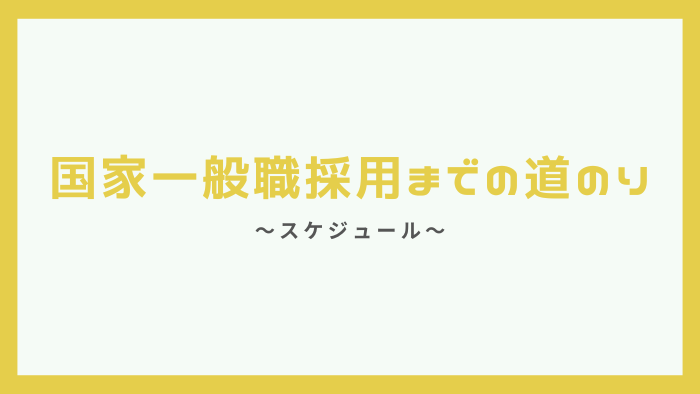
コメント