 ござる
ござるこんにちは、ござるです。



やばい、もう冬なのに何もしてない…
周りの友達が模試や勉強を始めている中で、焦りを感じていませんか?
大学3年の冬。
公務員試験を目指すには「ちょっと遅いのでは?」と感じる時期かもしれません。
でも安心してください。
正しいやり方で動けば、ここからでも十分に逆転は可能です。



実際、僕も冬スタート組でした。
最初は「無理かも」と思いましたが、勉強の“やり方”を変えら、一気に合格まで近づけました。
この記事では、そんな僕の経験をもとに
- 冬から始めても間に合う理由
- 短期間で効率的に伸ばす勉強戦略
- 時間がなくても狙える職種
をまとめました。
「誰でもまだ間に合う」──
その現実的なロードマップを、今から一緒に見ていきましょう。
結論|大学3年の冬からでも公務員試験は間に合う
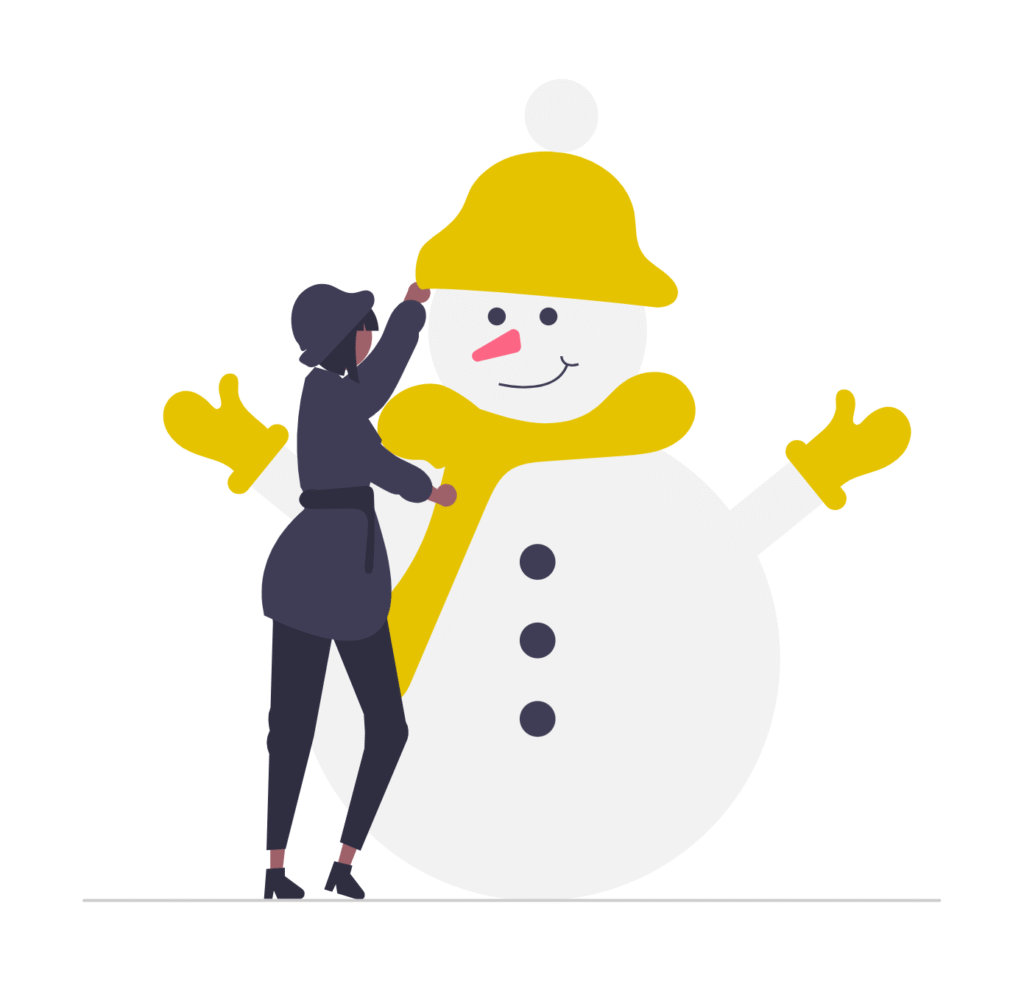
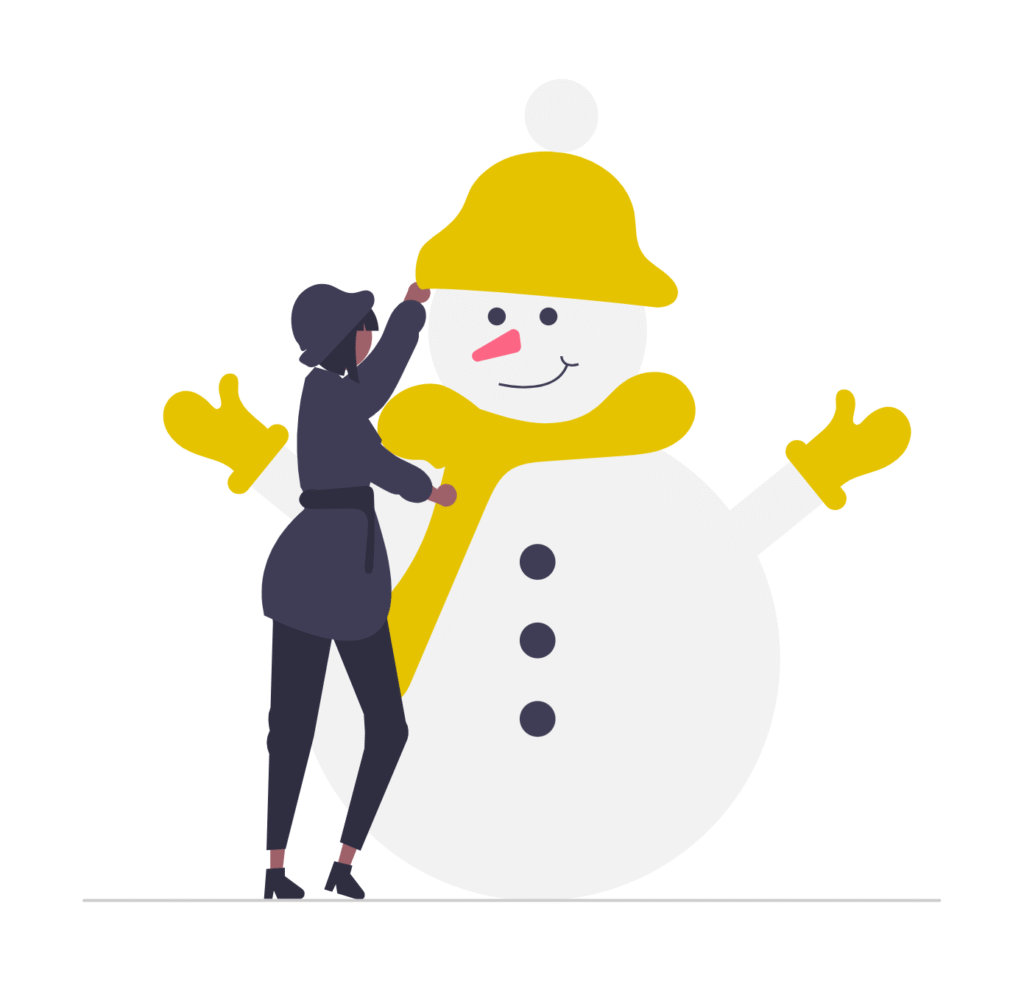



大学3年の冬からじゃ、もう遅いんじゃ…
そう思う人も多いですが、結論から言うと、まだ十分間に合います。
なぜなら、公務員試験に合格するために必要な勉強時間はおよそ1,000時間前後と言われており、
逆算すれば、冬スタートでも現実的に到達できるラインだからです。
📊 合格ラインまでの目安(目標時間)
| 勉強開始時期 | 試験までの期間 | 1日あたりの勉強時間 | 合計時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月前(12月ごろ) | 約180日 | 約5.5〜6時間 | 約1,000時間 |
| 5ヶ月前(1月ごろ) | 約150日 | 約6.5〜7時間 | 約1,000時間 |
| 4ヶ月前(2月ごろ) | 約120日 | 約8〜8.5時間 | 約1,000時間 |
こうして見ると、冬からでも「1日6〜8時間」を確保できれば、計算上は十分に合格圏に入れることが分かります。
もちろん、全員が同じペースで進むわけではありませんが、少なくとも「手遅れ」ということはありません。



直前期はワークライフバランスを捨てて馬車馬のように勉強してもらうけどね
-e1707016234779-150x150.png)
-e1707016234779-150x150.png)
-e1707016234779-150x150.png)
言いすぎでしょ!
💡 間に合う人・間に合わない人の違い
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| ✅ 間に合う人 | 勉強時間を“最優先”にできる人/得点源を絞って学習できる人/毎日継続できる人 |
| ⚠️ 間に合わない人 | 教材集めに時間を使う人/全科目を広く浅くやろうとする人/勉強ペースを週単位で崩す人 |
冬から始める人にとって一番大切なのは、「何をやらないか」を決めること。
限られた時間の中で、得点に直結しない作業を減らすだけで結果は大きく変わります。



“やらない勇気”も立派な戦略なんだよ!
🌱 そしてもう一つのポイント
時間が限られている分、「受かりやすい職種を狙う」のも立派な戦略です。
教養のみで受験できる職種や、SPI型を導入している自治体などは、勉強範囲が狭く、短期間でも現実的に合格が狙えます。



次の章では、そんな「短期間でも間に合う職種・試験区分」を紹介していきます👇
短期間でも狙える!受かりやすい職種・試験区分
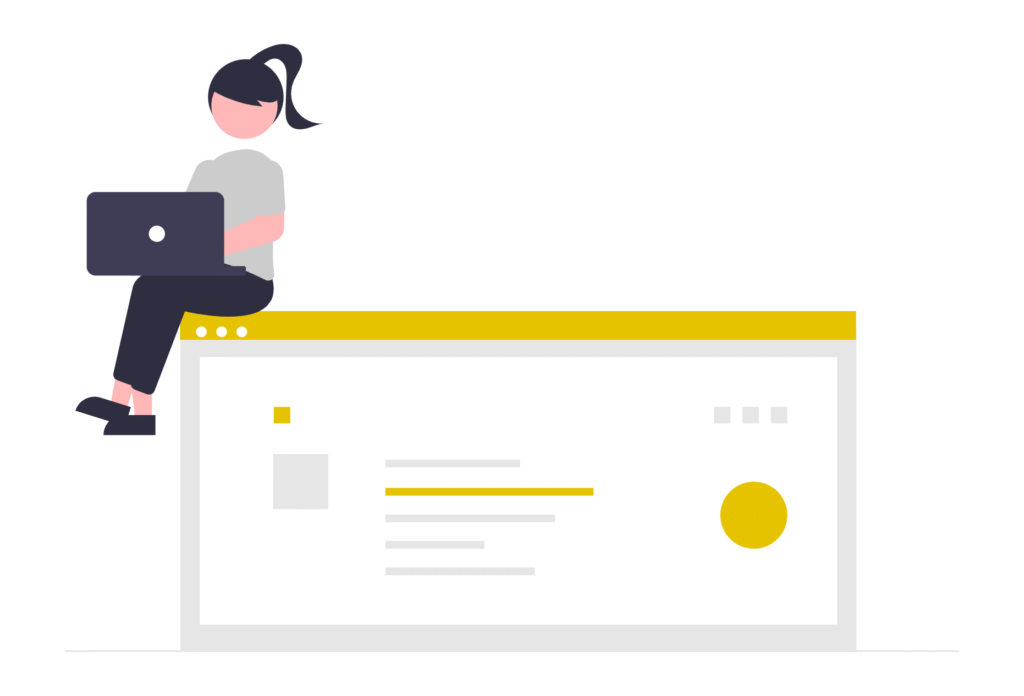
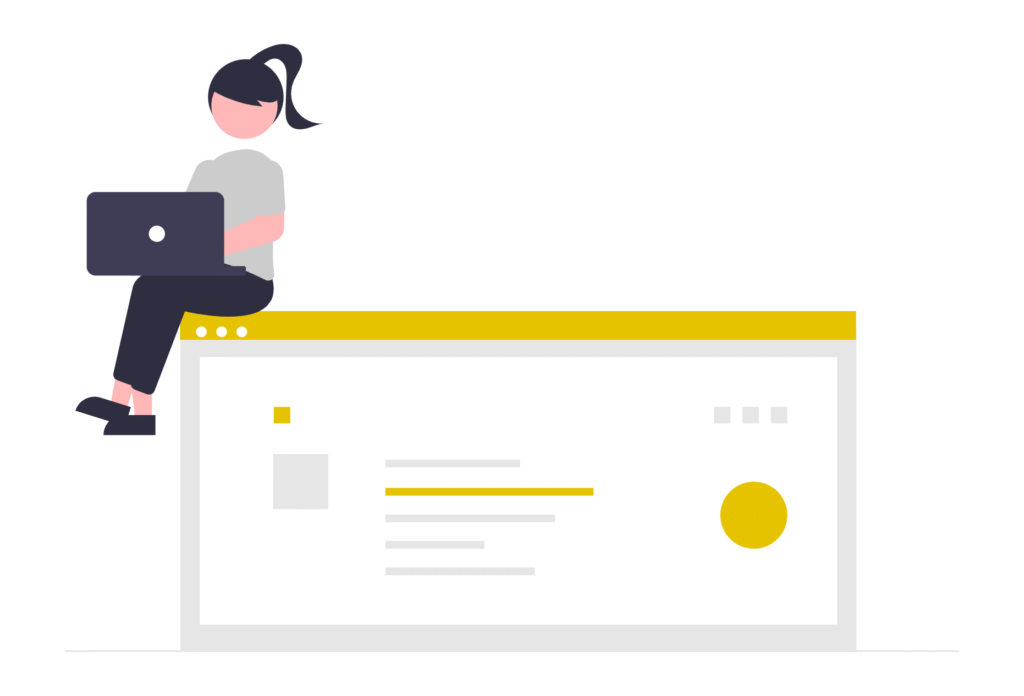
🧭教養のみで受験できる職種
筆記試験が「教養科目だけ」で受験できる職種は、冬からのスタートでも十分に狙えます。
代表的なのは、市役所・警察官・消防官など。
これらの試験は専門科目が不要な分、勉強時間を半分以下に抑えられます。
特に市役所試験は自治体によって出題傾向が似ており、参考書も豊富なので、短期間でも効率的に対策できます。
また、警察・消防は体力試験と面接が重視されるため、筆記で満点を狙う必要はありません。
「人物評価で巻き返せる」のも、冬スタート組にとっては大きなメリットです。



専門が苦手でもチャンスあり!“教養オンリー枠”は冬スタート組の救世主だよ
💬 SPI型で受験できる自治体
最近は、民間企業で使われる**SPI試験(能力検査+性格検査)**を導入する自治体も急増中です。
このタイプは筆記試験の難易度が低く、対策範囲が非常に狭いのが特徴。



50時間ぐらいで対策可能!
たとえば、東京都特別区や一部の市町村では、SPI型試験が新設されています。
SPIは民間就活と共通の内容なので、就活対策を兼ねて効率よく準備できるのもメリット。
ただし、人物評価(面接)の比重が高くなるため、面接カードや志望動機の完成度が勝負です。
「筆記で逆転」よりも、「人物で差をつける」戦い方を意識しましょう。



SPI型は“人間力勝負”。しゃべりが得意ならむしろチャンスだね!
🏛️ 2025年度から新設!国家一般職「教養区分」
2025年度の春から、国家一般職(大卒程度試験)に新しく「教養区分」が誕生しました。
これは、これまでのように法律・経済などの専門科目ではなく、一般教養を中心に受験できる新しい区分です。
試験内容も、従来の専門試験とはかなり異なります。
| 試験区分 | 概要 | 配点比率 |
|---|---|---|
| 基礎能力試験 | 文章理解・判断推理・数的処理など(30題) | 4/9 |
| 課題対応能力試験 | 速く正確に課題を処理するスピードテスト(120題/15分) | 1/9 |
| 一般教養論文試験 | 判断力・思考力を問う1題の論文 | 2/9 |
| 人物試験(面接) | 個別面接で人柄や対人スキルを評価 | 2/9 |
専門知識よりも、思考力・スピード・論理性・人物面を重視する内容となっており、
教養試験対策を中心にしている人には非常に有利な区分です。



国家一般職に“教養区分”ができたのは、冬スタート組にとって超朗報!専門なしで国家公務員が狙える時代きたね
より詳しく「狙い目の官庁や不人気官庁」を知りたい方は、関連記事の【国家一般職】受かりやすい&不人気官庁まとめ|穴場を徹底解説!もチェック!
🗓️ 試験時期が遅めの自治体を狙う
公務員試験は自治体ごとに日程がバラバラです。
たとえば、地方上級・政令指定都市・後期市役所は、試験が秋(9〜10月)に行われる場合もあります。
つまり、冬スタートでも実質7〜9ヶ月の準備期間が取れるわけです。
この「時期差」を利用して、同じ年に複数チャンスを作るのも賢い戦略です。



得点だけじゃなく“日程”も味方につけよう!
🪶ここまでのポイントまとめ
- 冬スタートでも“普通の試験”で十分間に合う
- 教養系・SPI型・新設区分を併願すればチャンスがさらに広がる
- 日程が遅い自治体を組み合わせれば、受験機会を増やせる
受けやすい試験区分を選ぶことで、合格までのハードルは確実に下がります。
冬スタート組の中でも落ちる人の特徴


この章では、「冬から始めて失敗してしまう人」に共通する特徴を紹介します。



一つでも当てはまる人は、今すぐ軌道修正しておこう💡
⚠️ 1.教材ばかり揃えて満足してしまう
失敗する人の典型が、 “準備だけ完璧タイプ”。
参考書や過去問、ノートを揃えて「よし、やるぞ!」で満足してしまい、実際の勉強に入るのが遅れるパターンです。
公務員試験は範囲が広いので、教材の数よりも使い倒す回数が勝負。
最初の1冊を信じて、まずは3周回すつもりでやり切ること。



勉強は“買う”より“回す”! これ鉄則!
⚠️ 2.インプット中心で過去問を後回しにする
「まずは基礎固めから」と思って参考書ばかり読んでしまう人も要注意。
いくら知識を詰め込んでも、問題が解けなければ意味がありません。
過去問に早めに触れることで、「何をどのレベルまで覚えるべきか」が分かります。
理想は、勉強時間のインプット3:アウトプット7。
知識を“使う練習”に時間を割くことが、短期間で伸びる最大のコツです。



最初は間違えまくってOK! 過去問は“失敗の場”だと思って使おう。
⚠️ 3.全科目に手を出してパンクする
焦るあまり、「全部の科目をちょっとずつやろう」として失敗するケースも多いです。
結果、どの科目も中途半端で得点につながらない…。
冬スタート組こそ、出題数が多い科目から徹底的にやるべき。
数的処理・文章理解・憲法・行政法・経済学、この5科目が最優先です。



“広く浅く”は一番危険! “狭く深く”から広げていこう!
🔍まとめ:やらかしパターンは早めに潰す!
| よくある失敗 | 正しい方向 |
|---|---|
| 教材ばかり集める | 最初の1冊を信じて使い倒す |
| インプット中心 | 過去問でアウトプット重視 |
| 全科目やる | 重要科目に絞る |
どれも「気合が空回りする」典型例。
今のうちに修正しておけば、同じ勉強時間でも成果は段違いです。



次は“どう動けばいいか”を具体的に見ていこう。ここからが本番だよ🔥
ゼロから合格できる!冬からの逆転ロードマップ
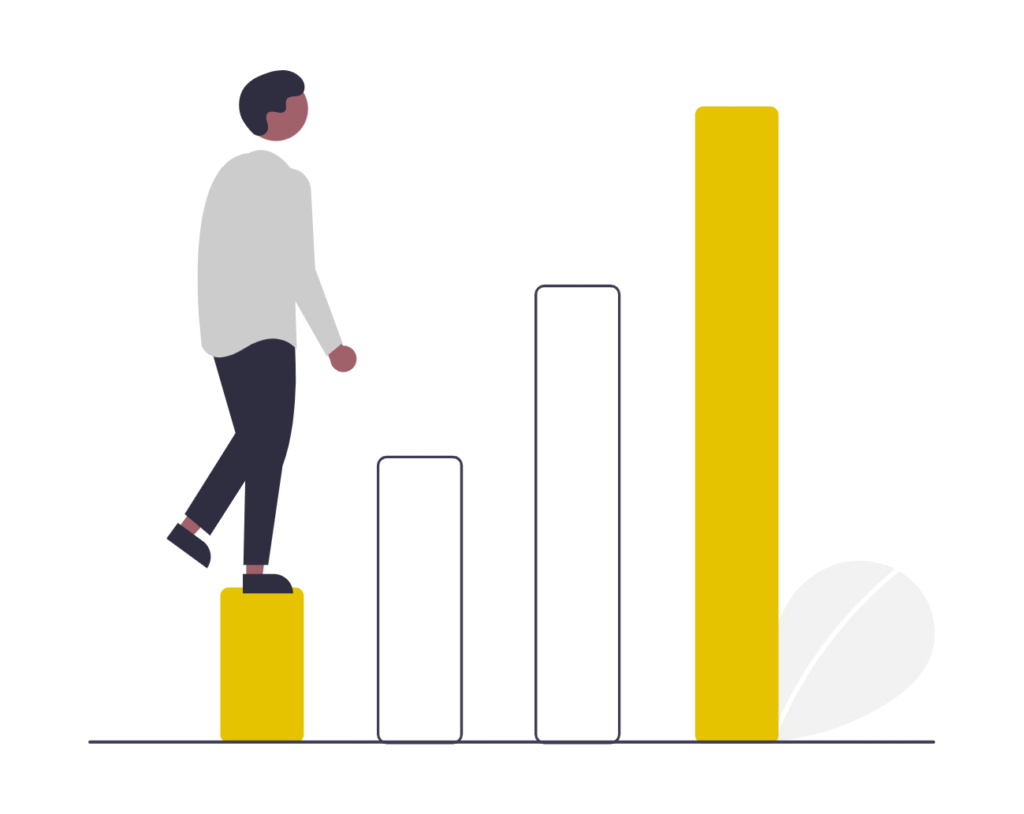
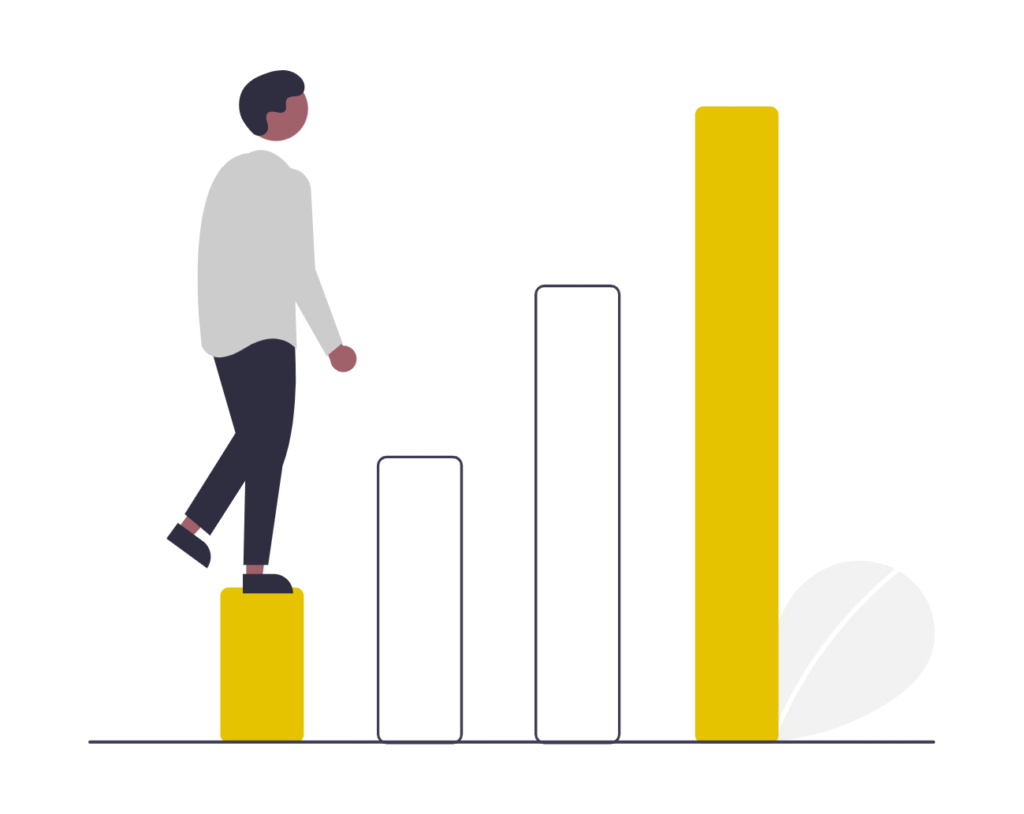
ここでは、ゼロからでも合格を狙える逆転ロードマップを5ステップで解説します。
👉通常の試験区分(国家一般職・地方上級・市役所など)を想定



ひとつずつ実行していけば、最短ルートで合格ラインまで到達できます🔥
🥇STEP1:ゴールを決めて勉強時間を逆算する
まず最初にやるべきことは、「目指す試験と残り期間の把握」。
試験日から逆算して、1日あたり何時間勉強が必要かを明確にしましょう。
通常の試験区分(国家一般職・地方上級・市役所など)→1000時間を想定
| 期間 | 目安の勉強時間 | コメント |
|---|---|---|
| 約6ヶ月前 | 1日5.5〜6時間 | 無理のない理想ペース |
| 約5ヶ月前 | 1日6.5〜7時間 | 現実的な合格ライン |
| 約4ヶ月前 | 1日8〜8.5時間 | 気合で追い上げるゾーン |
勉強量を“感覚”ではなく数字で見える化することが、最初のハードルを超える一番のコツです。



“あと○時間”って数字が見えると、焦りが行動に変わる!
📚STEP2:出題数が多い科目から着手する
限られた時間で結果を出すには、科目の優先順位付けが超重要。
公務員試験では出題比率が大きい科目から勉強すれば、得点効率が一気に上がります。
重要5科目(最優先!)
- 数的処理(判断推理・数的推理・資料解釈)
- 憲法
- 行政法
- 民法
- ミクロ・マクロ経済学
この5科目で、主要試験の得点の6割近くを占めます。
最初の2〜3ヶ月は、この5科目だけに集中してOK。



“広く浅く”より“狭く深く”。得点源を決めるのが最初の勝負!



専門科目って種類多すぎて悩むよね…。おすすめ科目をランキング形式でまとめた記事があるから、効率よく決めたい人は見てね👇


🧠STEP3:インプット3:アウトプット7の法則
勉強が進まない人の多くは、 “参考書ばかり読んで満足している”タイプ。
公務員試験は暗記ではなく、「問題を解けるようにする試験」です。
基礎を学んだら、すぐに過去問や問題集に取り組みましょう。
間違えてもOK、理解より“慣れる”ことを優先!
理想は「インプット3:アウトプット7」。
学んだことを問題で使う練習を重ねるのが合格最短ルートです。



最初は正答率低くても大丈夫!解きながら理解すればいいんだ。
⚡効率UPのコツ
短期間で結果を出すには、「勉強量」よりも「回転スピード」を重視すること。
以下の3つを意識すると、同じ時間でも成果が全然違います👇
| コツ | 内容 |
|---|---|
| ⏱️ 勉強を45〜60分で区切る | 集中力の限界を超えない範囲で細かく休憩を入れることで、記憶定着率が上がる。 |
| 📖 1日1テーマ方式 | 「今日は判断推理だけ」など、毎日テーマを決めて学ぶと迷わない。 |
| 🔁 問題を“解く→見直す→再挑戦”で1セット | 同じ問題を3回回すほうが、新しい問題を1回やるより効果的。 |
🕹STEP4:捨て科目をつくって効率を上げる
時間がない冬スタート組が全科目やるのはムリゲー。
出題数が少ない科目・苦手科目は思い切って捨てましょう。
- 出題数が1〜2問しかない科目
- 重要5科目以外で時間がかかるもの
- 自治体によって出題がほぼない分野
を優先的に“削る”ことで、得点効率を倍以上に上げられます。
詳しくは【最新版】公務員試験の専門科目「捨て科目」はコレだ!効率重視の選び方を解説で解説しています。



全部やろうとするのは“真面目な人ほどやりがちなミス”。割り切る勇気が大事!
🧩STEP5:面接・論文対策は“下準備だけ早め”がカギ
筆記試験で足切りされたら意味がない。だから冬スタート組にとっては、まず筆記突破が最優先。
→この考え方自体は正解です。
ただ、筆記後に面接準備をゼロから始めると、
「面接カード作り」「志望動機整理」「自己PR作成」に時間がかかって焦りやすい。
そこでおすすめなのが、筆記前に“考える部分だけ”済ませておくこと。
たとえば👇
- 自己PR・ガクチカのメモを残しておく
- 志望先の自治体・職種の特徴を軽く調べておく
- 面接カードの下書きを作っておく(完成度30%でOK)
これだけでも、筆記後のスタートダッシュがまったく違います。
「筆記が終わってから本格的にやる」前提でOKなので、この段階では“情報を整理する”くらいの感覚で十分です。



面接対策は“やる時期”より“考えてる時間”がモノを言う。筆記後に慌てないように“メモ貯金”だけしとこ!
✏️補足:論文対策も「型だけ」先に知っておく
論文も同じで、今から文章練習をする必要はなし。
論文試験1ヶ月前からでも全然間に合います。
ただ、
- 出題テーマ(時事・行政課題)の傾向
- 論文の基本構成(序論・本論・結論)
だけは早めに把握しておくと安心です。
🏁まとめ|大学3年の冬からでも公務員試験はまだ間に合う!
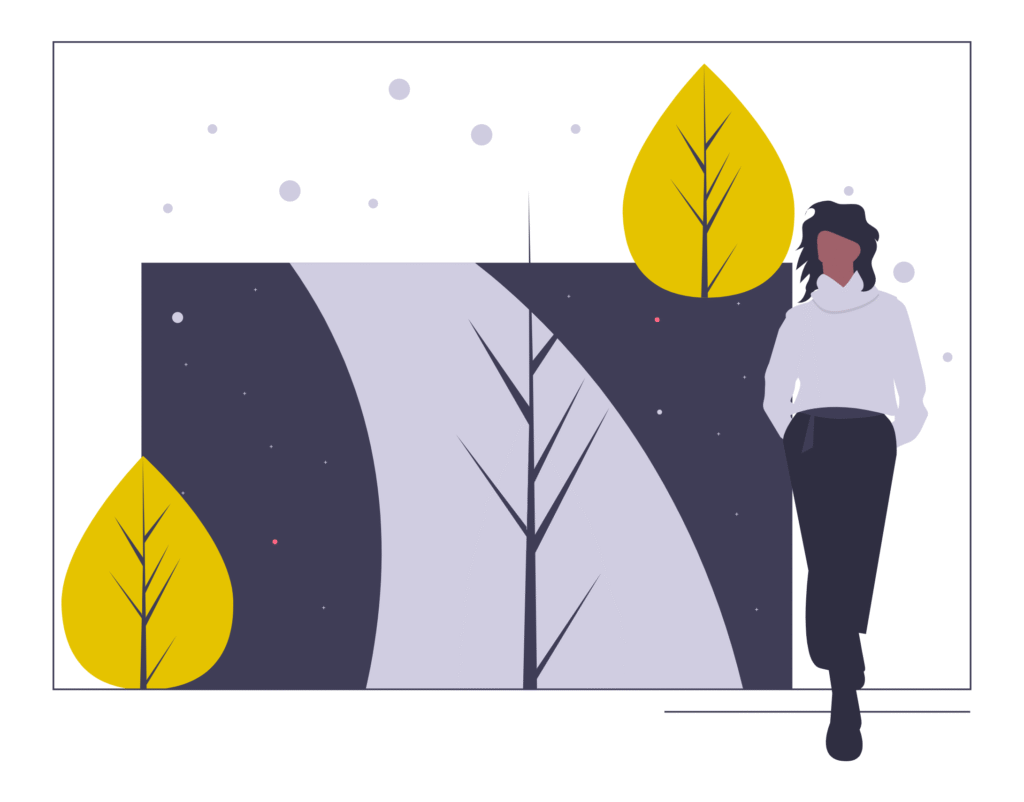
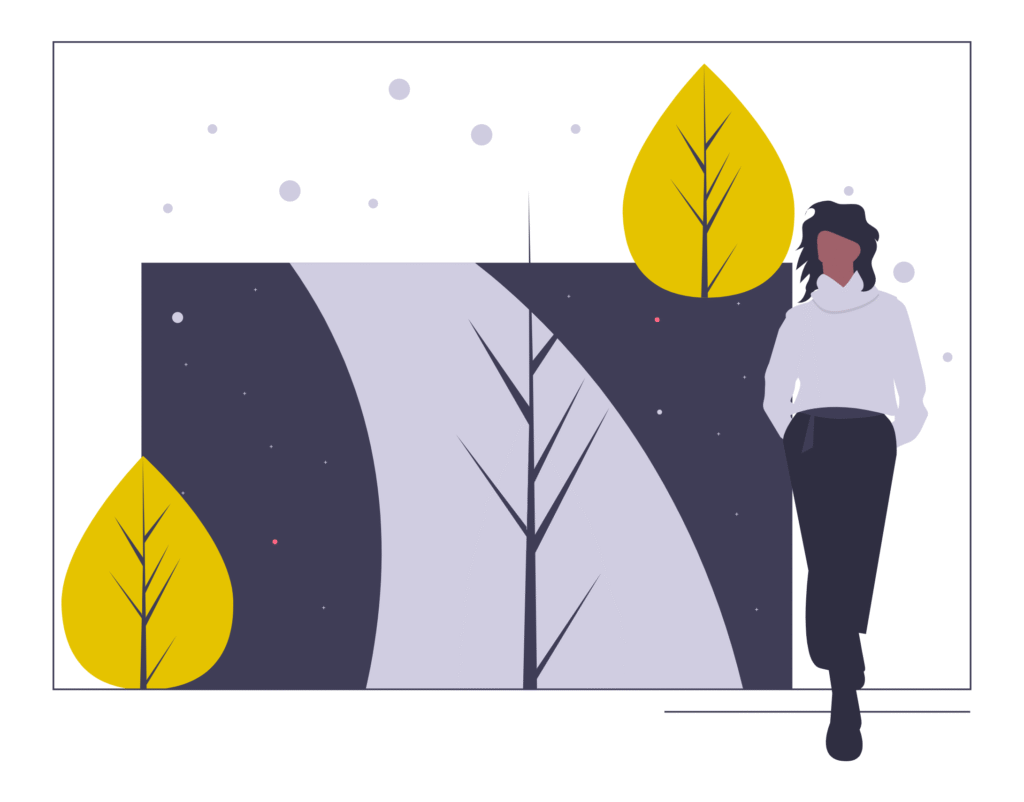
今回は「大学3年の冬からでも公務員試験に間に合うのか?」というテーマで、必要な勉強時間・戦略・職種選びのポイントを解説しました。
結論としては──
冬スタートでも十分間に合います。
ただし、限られた時間をどう使うかが勝負。
- 重要科目から効率よく勉強する
- 捨て科目で時間を生み出す
- 自分に合った試験区分を選ぶ
- 面接対策は“下準備だけ早め”に
冬からでも逆転合格は現実的に狙えます。
焦りや不安を感じている人こそ、
“今日から動き出すこと”が一番の合格戦略です。



今が“遅い”んじゃない。今が“スタートライン”だ!
⛄あわせて読みたい関連記事
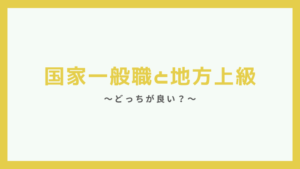
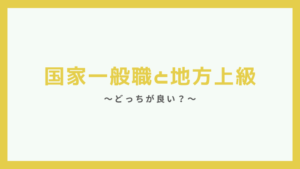
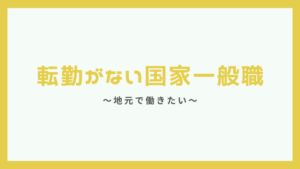
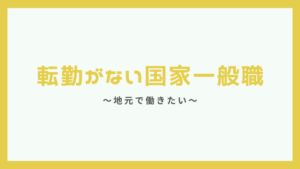


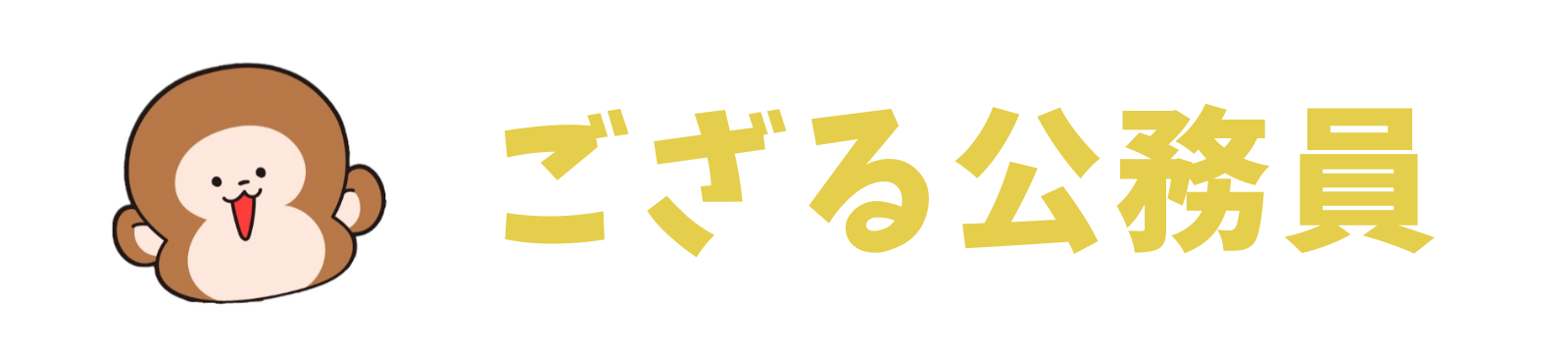








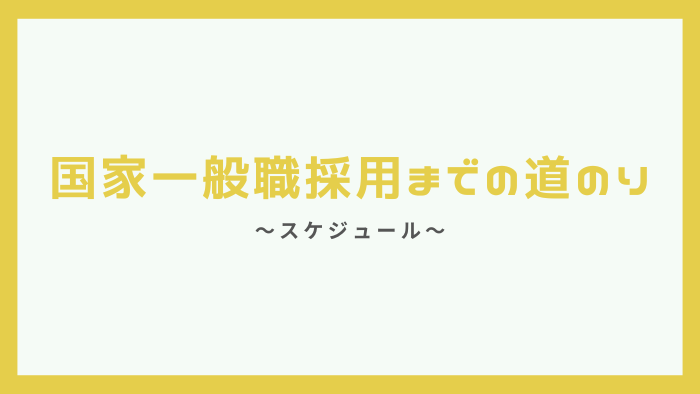
コメント